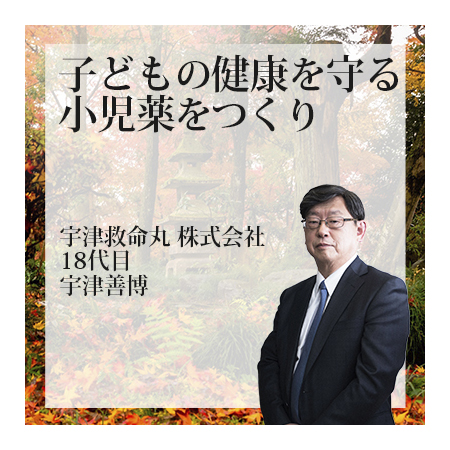
- 2020.10.02
宇津救命丸株式会社〜子どもの健康を守る小児薬をつくり〜
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは「宇津救命丸株式会社」、18代目 代表取締役社長 宇津善博。1597年創業。
小売店で買える、現存する薬の中では最も長い歴史を誇る「宇津救命丸」。
その知名度から「宇津救命丸」は小児薬の代名詞となり現在は、小児用医薬品の多数のラインナップを持つ。
今回は、400年以上に渡り、多くの人々に重宝されている「薬」を世に中に届け、伝統の継承、進化を続ける、宇津救命丸の代表、宇津善博の言葉から、事業継承の秘訣、その裏に隠された物語に迫る!
石田:本日のゲストは宇津救命丸株式会社 代表取締役社長 宇津善博さんです。宜しくお願いいたします。
一同:宜しくお願いいたします。
朝岡:皆様ご存知の宇津救命丸ですが、改めて御社の事業内容を教えていただけますか?
宇津:宇津救命を始めとする医薬品や、医薬部外品の製造販売、衛生材料及び医療用具・食品・日用品雑貨の製造販売業を行っています。
石田:宇津さんは何代目の代表に当たりますか?
宇津:私で18代目になります。
朝岡:早速ですが、こちらにある現在のお薬、商品を少しご説明いただけますか?
宇津:この宇津救命丸は創業当時からずっと400年間作り続けており、今日本で買える薬で一番古い商品になります。効能としては、子供の夜泣き、肝虫…今肝虫と言ってもピンとこないかもしれないですけど、今の若いお母さんとかはギャン泣きとか、ヒステリー的なかんじですね。子供の病気に治す薬です。
朝岡:この昔からの宇津救命丸以外にも色々お薬があるのですね。
宇津:400年間ずっと救命丸を作ってきたのですけど、私の代になって初めて、新しい風邪薬など多角的な商品を増やしてまいりました。
朝岡:ドリンクまであるのですね。改めて、この宇津救命丸という製品の強みとか特徴はどのようなところにありますか?
宇津:宇津救命丸というのは小さな丸剤になります。丸剤とは日本で一番古い剤型なのですが、角がない丸い剤型は飲む時に抵抗なく飲めるということで小さいお子さんやお年寄りなどに、一番向いている剤型になります。
全部生薬だけでできていますから、新薬のようにキナが強いとか患部に直接作用するとか、神経に作用するのではなくて、体を丈夫にして、自分の体の治癒力を高めて、病気を治すという考え方なんですね。ですから長く飲んでも体に副作用ないという特徴もあります。
ここからは、各テーマを元に、宇津救命丸18代目宇津善博の言葉から
歴史と伝統の裏に隠された「物語」、宇津救命丸が誇る「長寿の知恵」に迫る。
石田:創業の精神ということで、宇津救命丸さんの創業から現在に至るまでの経緯・歴史を伺えますか。
宇津:うちの初代は宇津権右衛門という人物だったのですけれども、下野国今で言う栃木県に宇都宮城というお城がありまして、そこの殿様の殿医でした。宇都宮城というのも長い歴史があるお城だったのですけれども豊臣秀吉の怒りに触れまして、お取り潰しになってしまった。
それでお城がなくなってしまい、今の弊社の創業地に帰農しまして庄屋になって収めましたと。村の人達の健康も考えて、お医者さんの知識を活かして救命丸を作って無償で配っていた。その効能が良くて求める人が増えてきたので、その後に販売するようになったと言う経緯になります。
朝岡:この赤ちゃん向けのお薬だけで400年というのもこれなかなか特別な歴史だと思うのですけど、それ以外の風邪薬などを扱うようになったのは最近のことですか。
宇津:そうですね。明治・大正・昭和と救命丸一本できたんですけれども、昭和の私が社長になる前の常務時代に救命丸だけでは将来難しいと思って風邪薬を考えました。
石田:18代目でいらっしゃるんですけれども、宇津家の家訓や理念はどういったものなんでしょうか。
宇津:家訓というのはないんですけど、理念というのは創業者の「無償で人々を助ける」という理念は今でも引き継いで「人々の健康に貢献する」という考えを今でも持っております。
朝岡:なかなか志から始まっても理念がずっと400年も引き継がれるっていうのはなかなか難しいと思うんですが、ここまで引き継がれてきた理由はありますか。
宇津:時代時代によって、そういう経緯かわかりませんが、例えば明治時代ではもともと大人向けの薬だったんですね。けれども当時の明治時代にお子さんの病気が非常に多くてときには命をなくすことも多いので当時の統帥が子供の健康を考えて、なんとかしようと小児薬に変えたわけですね。それもやはり初代の理念を貫いたということだと思いますね。
石田:こちらのお薬、「宇津救命丸」のお名前の由来を知りたいんですけれども、宇津さんなのでこちらの宇津救命丸なんですね。
宇津:薬のメーカーさんには古いメーカーさんがいくつもあるんですけれども、社名と商品名と名前が3つとも同じっていうのは珍しいですね。
私は宇津(ウツ)で社名は宇津(ウズ)なんですけれども、なんで違うかというと昭和の中期にテレビコマーシャルをやる時に「ウツキュウメイガン」だと聞きづらいと言うことで、それだけの理由で社名を「ウヅキュウメイカン」と変えてしまった(笑)。
朝岡:ほんとは、「ウツキュウメイガン」だからお名前ウツさん。でも確かにコマーシャルで言いにくいよね「ウツキュウメイガン」「ウヅキュウメイガン」なんか効きそうなかんじがしますね。それで「ヅ」になったんですね。でもそれって大きいことですよね。
朝岡:これだけ長い間親しまれている宇津救命丸ですが、いろんなエピソードというか逸話というかあると思います。できれば幾つかお伺いしたいんですが。
宇津:昔話になってしまいますけど、江戸時代にうちの領地を治めるのが一橋家という徳川御三家の方が収めてたんですね。うちが番所に近かったので救命丸献上していたんですね。
そうしましたら、当時の殿様が救命丸を非常に効能が良いということで自分の子供に飲ませる。お世継ぎを輩出しなければいけないので子供を非常に大切にされてたんですね。今までは大人が飲んでいた薬を初めて一橋家では子供に飲ませたという歴史があります。
それで、救命丸をストックはしていたんでしょうけどもしなくなった場合栃木県から江戸まで持ってこいというお達しがありまして、御用提灯を預かって鬼怒川を船で下りまして、途中から江戸川の船に乗り換えて、秋葉原の港についてそこから早馬で一橋家のお屋敷に届けたと。だいたい一日もかからずに届けられたらしいですけれど。それだけ信頼していただいていた。
石田:どういった製法で作られてるんですか。
宇津:今ですと、だいたい生薬っていうと皆さん粉末で買われる場合があるんですけど、うちの場合は生の生薬を買ってきてうちの工場に粉末にして、まぜて丸にするわけですね。
朝岡:そうですか。作り方自体も昔と今では随分変わってきている。生薬自体は変わらないですけど。
宇津:そうですね。丸を作るというのは、昔は手で作っていたんですけれども、今はもう機械で作っております。大正時代に丸を作る機械を開発した方がいらっしゃって、それが今の機械のもとになっています。
決断 ~ターニングポイント~
石田:決断、ターニングポイントということでまずはこれまでに起こった会社にとっての転機、ターニングポイントを伺えますか?
宇津:一つは江戸時代の話になってしまいますけど、当時は直接小売店に当社が全国に歩いて卸していたんです。それが明治になって今のシステムが出来上がりまして、直販から流通システムに乗せて販売するようになったのが一つの大きなターニングポイントだと思います。
二つめは、400年間続けていた救命丸だけから、新しい商品を出して今の多角化の線に切り替えたと言うことが二つめのターニングポイントだと思いますね。
朝岡:富山の薬売り屋さんというのは今でも直に売りますが、ああいう形を江戸時代にはおやりになっていて、簡単に言うと。明治からは所謂会社と流通が別という形になっていったと。それはなんとなく分かるんですね。多角化になっていったというのはまさに宇津さんがご自分で進めて、決断なさったターニングポイントだと思うんですけどね。いまから何年くらい前の話ですか、それは。
宇津:30年ぐらい前ですかね。私が社長になる前ですから。当時風邪薬を出そうということになって、父が社長だったんですけれども、社長も了解してやろうということだったんですけれども当時2種類の風薬を作る事になったんですね。
父は宇津救命丸で作る漢方風邪薬、私はこれからの時代味が良くないと売れないと思って、お子さんが喜ばないと思ってこういうようなイチゴ味の新薬系の風邪薬を開発してたんです。
同時に発売したわけなんですが、父は自分のところで作る風邪薬のほうが可愛いもんでコマーシャルなんかもそっちばかりにかけていたんですけれども、私が開発したイチゴ味の薬ほうが売れちゃったんですね。味がいいもんですから。これ(私が開発したイチゴ味の薬)を作るときにも私の子供が小さくて3人いましたんで、こういう薬の味見をさせて何が良いかと聞いくとイチゴ味が一番おいしいと言うことでイチゴ味に決定したんです。
皮肉なことにうちが作っていた漢方薬の風邪薬が子どもたちに非常に不評だったので、私は父にこれからはこういう(イチゴ味などの)薬で行かなきゃダメだということで非常に喧嘩になりまして。私が生まれて35年父に対して口答えをしてこなかったんですけれどもこのときは大喧嘩になりまして、父にこの会社からお金もらってるのか!うちの会社がどうなっても良いのか!と言われて非常にショックだったんですけれども…。
朝岡:それは、こういったイチゴ味のもととなるような会社からお金貰って、うちの生薬の漢方薬、救命丸はどうなるんだということですよね。
宇津:そうですね。ただうちの父もバーっと怒鳴ったりするんですけどすぐに反省してしばらくしてから電話がかかってきて「お前の好きなようにやってみろ」と(言われて)すぐにこの(イチゴ味の)薬のコマーシャルをかけたら非常に大ヒットしまして、店頭からなくなってしまって入荷待ちみたいな形になってしまいました。
石田:確かに飲みやすいのはポイントですもんね。
宇津:当時子供の風邪薬は一応あったんですけれど、デザインが悪いとか、味が美味しくないとか、名前も「小児用漢方薬」みたいに、あまり重視されてなかったんですね。うちは私が子どもたちに飲ませてた時に、楽しく飲める薬が造れないかと思って覚えやすい「子供風邪薬」という名前とか、カラフルなパッケージや、イチゴ味にするとかを発売したんです。
それがその後、他社さんも出されたもののスタンダードになって、今の子供向けの風邪薬はカラフルなパッケージになってきたんですね。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
石田:続いては言魂ということで、幼いころ先代や祖父母から言われれた印象的な言葉、そこに託された思いを伺っていきたいと思います。
宇津:私の祖母が直系だったんですね。嫁ではなく直系だったので祖母によく「お前が救命を継ぐんだよ」と言われたのは覚えてます。
朝岡:やっぱりおばあちゃんから言われると特にちっちゃい時はそうかなーって思うしかないですもんね!
宇津:そうですね。
朝岡:それは(祖母の言葉)年齢が大きくなるにしたがってもどこか心の中にはあったんですか?
宇津:薬大に行ったあたりから会社を守ってかなくてはいけないという気持ちはありました。
石田:そうなんですね。そんな中で、学生時代に他に目指されていた職業があったりしましたか?
宇津:特には考えてなかったですけど、自衛隊には一度入ってみたいなと思いましたね。そういうのは興味があったのと、規律を学べるのではと思いまして。しかし結局は、周りにガツンと言われてしまって断念しましたね。
朝岡:しかし組織とっては、規律が大事な部分ではありますよね。今現在、ご自身が大切になさっている言葉っていうのがあったら教えていただきたいです。
宇津:「常に正直であれ」という言葉です。「正直者は馬鹿を見る」って言葉がありますけど、私はすごく嫌いな言葉でして。現実的にはそういうこともあると思いますが、経営に関しては正直に行かなければ行けないと思います。
朝岡:いろんな意味でお客さまとか、お薬を買って下さる方への正直な部分、それから会社の中とかお薬そのものに対して正直であるという色んなことがあると思うんですね。
宇津:生薬ってのは自然のものなので、ピンからキリまであるんですね。どれを使っても問題はないんですけど、うちはいつも純度の高い生薬を使うようにしています。
というのも私も薬剤師なので会社に消費者相談でかかってくる電話に私も出ることがあるんです。お母様方が藁を掴む気持ちでうちの救命丸やお薬を買いたいんだけどという気持ちがあれば、紳士に答えていきたいという気持ちはありますね。
貢献 ~地域、業界との絆~
石田:宇津救命丸さんがやっていらっしゃる地域との取り組みですとか地域貢献活動を伺えますでしょうか。
宇津:敷地の中に薬師堂というのがありまして、1年に1回お祭をやっていたんですね。薬師堂っていうのは健康の仏様薬師如来を祀っているんですけど、江戸時代から人々の健康を祈願してお祭りを地域のお祭りとしてずっと続いてたんです。結構大きなお祭りだったんですけど、だんだん昭和になってきて色々環境が変わってきて自然にやめてしまったんです。
うちの息子が2011年の東北大震災の時地元の被害が多かったもんで、復興を祈ろうということで薬師堂を復活させたんですね。それ以来不定期ではあるんですけど、地元の町とか商工会とか観光協会とかと一緒になって町のお祭りとして継続しています。うちのイメージ的なものから子供祭りということで幼稚園・保育園の園児さんにお神輿を担いでもらったりイベントをやったりして地域に多少でも元気になってもらえればと思いましてやってますね。
朝岡:企業のイメージとしてもね、お子さんの薬を扱っていらっしゃる会社だから。お子さんたちの笑顔が広がる祭りというのは、とてもプラスになる気がしますね。
宇津:私の時はコマーシャルをやってましたのでどっちかといえば目が全国を見ていてあまり地元を見てなかったんですね。だけど息子に教えられたというか息子が地元も大事にしなきゃいけないという事で、地元の商工会、地元のホランティアにも参加するようになりました。
朝岡:長寿企業にとって地元とか地域とのつながりは改めて注目されている時代と思ってよろしいんでしょうか。
宇津:お祭をやって初めてわかったんですけど、救命丸ってうちの街にあったんだねって知らない方が結構いるんですね。というのも住所が東京になってるもんですから金沢にこういう会社があったって知らなかったとか、この街にあって非常に誇らしいとかそういう声を聴くと報いていかなければいけないなと思いますね。
石田:地域とのつながり絆を大切にされていると思うんですけど、同じ業界のつながりというのはあるんですか?
宇津:はい。我々歴史の長いメーカーは家庭薬って呼んでるんですね。東京に約50社ほど家庭薬が集まった「東京家庭薬組合」というのがありましてその中でいろんな活動をして会員のために薬事のこととか労務のこととか、そういうことで委員会を作って会員のために勉強会なんかを行っています。
朝岡:それは昔ながらの家庭薬の販売形態をまとめようというのがきっかけだったんですか?
宇津:随分前の話で私は当時のことはわからないんですけど、新薬メーカーさんがどんどん台頭してきたんですね。それに対抗するために家庭薬でまとまって何かをやるってことで組合を作ったと聞いています。
朝岡:お薬とか売り方もお薬自体も違いますからね。
伝燈 ~受け継がれる伝統~
朝岡:これだけ歴史のある会社だと色んな言い伝えというか、モノとか家訓を懐中した巻物とかはないんですか?
宇津:身近に置いているのはずっと伝わる印籠なんですが。いつからかはわからないんですけれども、うちに伝わる印籠で、印籠っていうのも薬入れなんですね。開けると薬が入っていて。旅なんかに持っていって薬を飲むという。
朝岡:ちょうど帯のところに入れてるんですね。この紋所は、中に本当に薬が入ってるんですか?
宇津:昔の救命が入ってます。もう色変わってますが。
NEXT100 ~時代を超える術~
石田:次の100年に向けて、変えるべきもの変えないもの、御社にとってコアになる部分を教えていただけますでしょうか?
宇津:変えない部分としては、昔からある丸剤をずっと続けていきたいと思っています。少子化なので子供の薬ばかりではなかなか難しいところがあるので、今方向転換はいろいろ考えてはいるのですが、やっぱりいくら子どもの人口が少なくなっても子どもの健康を守る小児薬はつくり続けていきたいと思っています。
朝岡:これから100年たつと宇津救命丸もまた新たなフィールドを広げている可能性が大きいと思うんですけど、その時の会社の後継者、リーダーに何か伝えておきたいこと、かけてあげたい言葉があったらお聞かせいただけますでしょうか。
宇津:経営に対しては真摯に向き合えということですね。初代の人々の「貢献する」という精神を忘れずに、正直に経営してもらいたいと思います。
石田:真摯な経営とは、具体的にどういったものを指すのでしょうか。
宇津:本当に一例なんですけど、消費者から「救命丸買いたいのですけど売ってないんです。どこに売っていますか。」というお問合わせがある。うちは徹底的に調べてどこに売ってるか調べてお時間いただくんですけど、そのお店に連絡してこういう所に売ってますっていうケアしてるんですね。
これは私が経験したことなんですけどある企業さんに電話して聞いた所、非常に難しい答えが返ってきたり、冷たくされたりするんですけれども、やはり消費者にとってこれはいけないなということを実感したのでそういうところは消費者に合わせてやっていきたいなと思ってますね。
朝岡:一人のお客さまでも正直に対応するということになるんでしょうね。それにしても400年を超える事業が続いているというのは、ご商売以外を見ても非常に珍しいことでもあるんですが、改めてこれだけ長く続いてきた宇津救命丸の大事なポイントっていうのはなんですかね。
宇津:子どもに特化してきたていうのが一つのポイントだと思うんですけど、これが良いか悪いかは別の話でして。家庭薬っていうのは例えば心臓の薬のメーカーさん、喉薬のメーカーさんってあって、そのシェアはトップなんですけれどもそれが逆に他の分野にいく時に足かせになる。うちも子供の薬というイメージを持たれているので、なかなか他の商品を出す時に難しくなっている場合もあります。
朝岡:良いところとちょっと勇気がいる所、これからどう100年続ける中で変えるのか変えないのかまた考えていく課題はあるってことですかね。
宇津:それはもう息子に任せる時代に任せないといけないと思うんですけど、私ももうそろそろバトンタッチをしないといけないので、未来を見据えて方向性を決めて、それから交代をしたいと考えていますね。