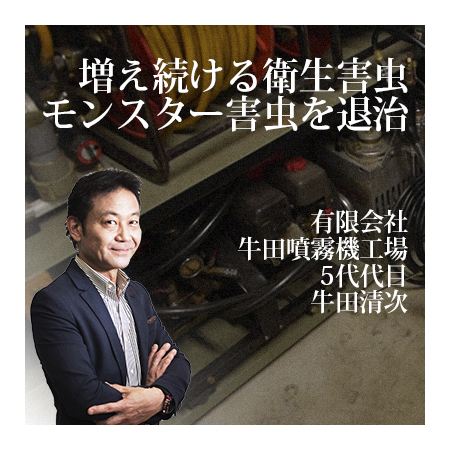
- 2020.10.03
牛田噴霧機工場 〜増え続けるあらゆる害虫を退治
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは、有限会社牛田噴霧器工場5代目 牛田清次(うしだ せいじ)。
明治44年(1911年)創業、その長い歴史の中で一族が守り続けたのは人々の“生活環境”であった。
農業用噴霧器の製造・販売会社として歩み、現在では『害虫駆除』など、時代が求めるサービスを提供する。そこには常に追求された“利便性”と“操作性”そして、106年を数える歴史に裏打ちされた“確かな技術”が存在していた。
今回は、代表取締役・牛田清次の言葉から、牛田噴霧器工場が紡いだ「歴史の伝統」に隠された物語、長寿企業が誇る「長寿の知恵」の真髄に迫る!
石田:本日のゲストは有限会社牛田噴霧器工場 代表取締役社長の牛田清次さんです。
朝岡:事業内容は噴霧器を作っているのですか。
牛田:もちろん噴霧器の製造と販売を行っていますが、それと同時に害虫・害獣の駆除と予防のサービスを行っています。
朝岡:よくテレビでもシロアリが出たとか、穴熊がでたという話を聞きますが、そういった害虫・害獣を駆除するお仕事をなさっているということなのですね。今何代目ですか?
牛田:今、私が5代目になります。
石田:そして、牛田さんが普段使われているのがこちらの商品(噴霧器)ですね。
牛田:こちらは私が力を込めて作り上げた商品です。見た目を一般の方々が見る機会はないですよね。こちらは2Lのサイズで、ステンレスで丈夫に作られています。今までになかったこととして、作業時に隙間まで噴射できるように、ノズルの先が360度回ります。散布するときには、固定式だと届かないところがあるのですが、この製品はそんな手の届かない痒い所にまで、届くようになっています。
石田:こちらは?(伸縮する棒を指さす)
牛田:こちらもプロ仕様で、伸縮するものになっています。私たちは、厨房や工場系の消毒をすることもあります。その時に、隙間に食材などの残渣があるんですけど、それをこの機械で掃除します。食べ物の残渣などをそのままにしておくと害虫・害獣が発生してしまいます。
石田:他にもかなり大掛かりな機械もあるのですね。
牛田:これは大きさがありまして、タンクが5Lあり、泡を使って製鋼するものです。というのも、通常、厨房などを掃除するとき、表面にアブラが付いていて、せっかく吹きかけても綺麗になりません。しかし、泡を使うことによって、そこに吸着する時間も長くなり、害虫たちへの接触率も高くなります。新しく開発された駆除方法の一つです。
朝岡:プロ仕様とありましたが、牛田さんの商品は、専門のレストランや、農家などの方向けの商品なのですか。
牛田:そうです。そのために耐久性にも優れ、利便性も追求したものを作っています。
石田:どのくらい種類があるのですか。
牛田:種類は、大きいものから小さいものまで、20~30種類くらいですね。
石田:用途に合わせて、噴霧器や中のお薬が違うという事ですね。
牛田:そうですね。施工方法はどんどん変わってきています。人間に対する毒性をないものにしようということで、ポイントによって変えなくてはいけない部分があります。そのような意味で用途によって種類があり、使い分け、消毒します。
朝岡:牛田さんは噴霧器を開発し、販売するだけでなく、これを使って実際に駆除しに行くのですよね。
牛田:はい、行っています。厨房や工場へ行き、私自身が作業する中で、もっとこんなものがあれば便利だなということを考えています。アイデアを出すのは大好きなので。
朝岡:製品開発の方法はご自身の経験から作られたものが多いのですか。
牛田:弊社は昔からずっと噴霧器を作っていたので、基礎はありました。そこに先端部分の仕様変更をすることで、劇的に変わるものもありました。そこを追及して、自分で実際に使い、実用性を体感しています。
朝岡:伝統だけでなく、ご自身の経験からのアイデアを加え、作業していくのですね。
長寿企業の創業から現在に至るまでの経緯、家訓や理念、その裏に隠された想い、「物語」に迫る。
石田:創業の精神ということで、牛田噴霧器工場の創業の精神をお教えください。
牛田:明治44年、私の大叔父が開業しました。当時、農業用噴霧器のみを扱っていました。その後、昭和に入り、私の祖父が2代目を継ぎ、噴霧器を皆さんに知ってもらいたいと、展示会を多く行い、拡販を試みました。その後、昭和の経済成長期に、3代目として私の父が継ぎました。そこでは噴霧器の販売を行いつつ、樹木消毒も行いました。経済の成長に伴い、樹木などの害獣の駆除も必要となり、役所の仕事などをいただきました。具体的には、都内の小中学校の樹木に毛虫がつかないようにするなどです。ここが施工を行い始めた時期です。
それから平成に入り、4代目として私の兄が継ぎました。今度は樹木だけでなく、飲食店や工場の衛生害虫の駆除も行うようになりました。この時、外食産業もドンドン伸びていたので、大手の飲食店と契約を結ぶこともできました。そして5代目として私が継ぎました。しかし、私自身は昔からこの仕事をしていたわけでないので、もっと他のものとコラボ出来たらなと、今までと違う見方を持って取り組んできました。
朝岡:会社も様々な変化をしていますが、明治44年、初代が噴霧器に目を付けたのはどうしてなのですか。
牛田:戦後、都市部でも農業が中心だったので、農業に伴った農薬散布が必要だったのです。そこに先代は着目し、噴霧器を開発したのだと思います。
朝岡:御社の経営は代々牛田家が行っているのですか
牛田:はい。5代とも牛田の名前で行っております。
石田:現在従業員が2名で、営業から現場の作業まで少数精鋭で行っているとお伺いしたのですが。
牛田:そうですね。ある程度人数が多くなってしまうと私自身の考え方も届かなくなってしまう。加えて、私たちの業界の面白いところは大きな仕事だと何社かで協力して、作業を行うのです。私たちは優れたスタッフを有しているので、そのような現場で統括を行います。従業員が大人数や、少人数でも違った問題はあるのですが。大きい仕事でも協力を仰げるので、成り立ちます。
朝岡:社員さんというより、職人さんに近そうですね。少し特殊な業界に思えますね。
牛田:そうですね。少し変わった業界かもしれません。業界自体もそこまで大きいものでないので、情報も限られた部分にしかないですね。
朝岡:社名にも入っていますが、噴霧器って知らない人も多そうですよね。
牛田:そうですね。余談ですが、お店に「牛田噴霧器です。本日消毒に伺いますね。」って言うと「何屋さんでしたっけ。」とかありますね。
朝岡:社名を変える話がないのですか。
牛田:兄の時に、横文字を使う社名にしようかという話がありました。しかし、せっかく伝統がある会社なので、先代の想いを残そうと、社名を継続しています。
石田:家訓や社訓はございますか。
牛田:私たちは“迅速に確実に作業する”“お客様の笑顔が見たい”というポリシーを持っています。これは近年海外からの輸入雑貨などに入り込んでいる衛生害虫。つまり、外来種です。以前まではそこに生息していなかったが、温暖化により様々な地域で生息できる害虫たちが増えています。情報がない害虫って怖いですよね。そんな時、私たちの技術や知恵で解決でき、お客様が喜んでくれる。その様な瞬間を大事にしています。
朝岡:自分で作業されるということで、それが生きがいみたいなものなのですね。
牛田:そうですね。やはり達成感がありますね。
石田:そのポリシーは代々受け継がれてきたものなのですか。
牛田:そうですね。今まで業務用の卸などがメインだったのですが、私の父の代に、お客様のところへ実際に向き合うようになった時から、この言葉が言われています。
朝岡:技術的な面も継承するには多くの課題がありそうですね。
牛田:もちろん、時代と共に薬剤の使用法などは変わっています。その中で伝統を残しながら、新しいものにも順応していかなくてはいけません。
朝岡:通常は、社長と職人って別になりますよね。
牛田:実際作業しなくては伝えることは難しいですからね。作業の体験をもとに、私も指示を出すことができます。
石田:動物だと、駆除する対象はどのような種類なのですか。
牛田:そうですね。動物だと駆除する種類によって役所に届け出が必要です。ネズミとかは問題ないのですが、例えば、鳩などは特別な申請がいります。他にも今までやったことないような種類の駆除の依頼もきますね。
朝岡:害虫・害獣駆除メインになると、噴霧器はもういいかなとはならないのですか。
牛田:ならないですね。実際、施工するうえで必要な道具があります。私たちも職人よりなので、道具にもこだわりたいというのはありますね。
決断 ~ターニングポイント~
会社にとっての転機、経営者自身のターニングポイント、その裏に隠された「物語」とは?
石田:牛田噴霧器工場のターニングポイントを伺えますか。
牛田:大正12年の関東大震災、第2次世界大戦を越え、戦後アジア向けの家具の輸出を行っていました。展示会に向け用意していたのですが、経営が傾き、ここで多額の借金が出来てしまいました。昭和20年から30年くらいのことです。なぜ、そうなってしまったかというと、輸出に関して、当時情報があまりなかったので、詐欺のようなことにあってしまいました。大量の数量を出したが、全く利益が入らない。これで大分傾いてしまいました。
朝岡:再建は上手くいったのですね。
牛田:今まで人力式の噴霧器だったのですが、高度成長期に伴い、農業も拡大しました。大手の動力噴霧器、広範囲に散布できる機会がどんどんシェアを伸ばしていました。いい機会なので体制も変えてしまおうと、専門のポンプメーカーと組んで、独自の商品を開発し、同時期に施工も行い始めました。結果これが幸いして、会社の中に指導型の害虫駆除業務も始めました。弊社の知恵や技術を教えるのと同時に、商品を販売していました。
石田:社長ご自身のターニングポイントをお伺いできますか。
牛田:私は二人兄弟の次男です。小さい頃から家業を見てきました。母からは兄弟二人とも同じ事業をしては共倒れしてしまうかもしれないので、好きな道に行きなさいと言われていました。ですから、自分で独立するなど、好き放題していました。当時は、まさか牛田噴霧器に携わるとは思ってもいませんでした。しかし、4年前に3代目の父が倒れ、4代目の兄も脳への障害が出てしまいました。牛田を守るのは僕しかいないのかなと、そこで継ぐ決心を決めました。
朝岡:4年前までは全く別のお仕事をされていたのですか。
牛田:私自身、学生を卒業した後、ペットのトリマーの資格を取得していました。ご縁もありまして、外資系のペットフードの輸入の販売をしていました。さらに、そのノウハウから海外のインテリアの輸入販売も行っていました。モノを作り上げるのが好きでして、靴のメーカーの知り合いから、手伝ってくれと言われて、実際テレビの前で販売したこともありました。私自身軌道に乗ってきていた時に、このようなことになってしまいました。当時の取引先に事情を伝え、少しずつフェードアウトしていきました。
石田:180度違う世界へ行くのは、かなり葛藤があったんじゃないですか。
牛田:そうですね。仕事を新しく覚えることも多くありましたし、牛田の名前を汚してはいけないという想いもありました。新参者として馬鹿にされてはいけないと日々勉強でしたね。
朝岡:営業など、過去のお仕事が現在に役立っていることもありますか。
牛田:そうですね。お客様に商品の良さを伝えたいという気持ちは同じで、今の仕事と結びつく部分はありますね。
朝岡:この噴霧器を作って販売し、駆除するなどにおいては、どのような性格が向いているのですか。
牛田:探求心だと思います。限界を決めないことですね。同じ現場は存在しないので、追求することは大事ですね。
石田:使われる機材や、薬の選択も大事なのですよね
牛田:そうですね。現在、環境に優しく人に害のない薬もありますが、だからと言ってむやみに撒いてもいけません。そこで、技、技術、処理法をしっかり身につけないとプロではないですよね。害虫・害獣がどこに生息し、どこまで入り込んでいるのかなどの知識も必要ですよね。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
先代・家族から受け取った言葉、そして現在、自らが胸に刻む言葉とは?
石田:先代やご家族から言われた印象的な言葉、そこに隠された想いなどお伺いしてもよろしいですか。
牛田:創業者の牛田清郎。この方は誠実で、勉強熱心で探求心もあり、非常に素晴らしい方で、幼少期からあのような人になりなさいと言われていました。その中で、あなたは清郎さんの生まれ変わり、ということも言われていたました。なぜかと言うと、私自身昭和39年に生まれたのですが、清郎さんは私が生まれるちょうど1年前に亡くなりました。清郎さんの残した功績は非常に優れていたので、清郎さんのようになりなさいと、静郎の漢字から“清”の字を受け継ぎ、清郎の“次”ということで“清次”という名前になりました。あなたは清郎の生まれ変わりで家業をやって欲しいということでした。実際4年前家業を継いだ時には、やはり運命を感じましたね。
朝岡:いつ頃から清郎さんをプレッシャーでなく、上昇機運としてとらえるようになりましたか。
牛田:清郎さんはコツコツと愚直に進むタイプでした。私はどちらかというと一気に進むタイプなので、実際に意識するようになったのは30代入ってからですね。起業して自分自身の責任を感じるようになってからです。
石田:牛田さんが心にとめている言葉はありますか。
牛田:“有言実行。やらねば明日がない”という言葉です。私自身やるのであれば最後まで成し遂げたいという気持ちを強く持っています。昔、営業をしていた時、できないことをできると言って失敗し、そのことがトラウマになっていたことがありました。なぜあの時最後まで出来なかったのだろうと。その教訓から“有言実行。やらねば明日がない”という言葉を大切にしています。
貢献 ~地域、業界との絆~
長寿企業にとってかかせないもの、それは、地域との関わり。そして、業界での絆。牛田噴霧機工場が行ってきた取り組み、地域貢献や社会貢献を行う中で牛田清次が感じた想いとは?
石田:現在、地域で取り組んでいることはありますか。
牛田:現在は直接地域の為に行っていることはないのですが、平成7年、淡路大震災の時、建物倒壊した瓦礫などで衛生環境が悪化しているということがありました。その時、3代目が手軽に使える噴霧器を150台寄付したということがありました。その後、市長さんが実際にその現場を案内してくれたと聞いています。
朝岡:日本は非常に災害が多い国です。災害の後に伝染病が流行したり、環境が厳しい時に、噴霧器というのは改めて見直されそうですね。さらにそのような寄付を通じて、認知も広がっていきそうですね。
牛田:そうですね。社会の為になるような開発が出来ればと思っています。
石田:業界の仲間同士でも社会に対して取り組んでいることはあるのですか。
牛田:北は東北から南は九州まで、私たちのような衛生問題に取り組む企業が50社ほど集まっている環境ビジネス研究会というものがあります。何をしているかというと、同業者同士ライバルでもあるのですが、良き相談相手でもあります。困っていることは同じですから。さらに目指すところは、お客様に喜んでもらうこと、よりクリーンにすることです。2ヶ月に一度集まり勉強会をしています。
朝岡:いつごろから行われているのですか。
牛田:平成12年に発足しました。当時4代目の私の兄が代表でした。
朝岡:同業者同士だと自社情報が洩れるという心配はないのですか。
牛田:そうですね。同業者なのでその辺りの駆け引きはありますが、やはり、最近はどの辺りで何が流行っているかなどの情報は交換し合います。害虫駆除のことだけでなく、今後はどのように業界が進んでいくかなども勉強していますので、いい会になっていると思います。
NEXT100 ~時代を超える術~
次の100年に向け、長寿企業が変えるべきもの、変えないもの、会社にとってコアになるものとは?
100年先の伝承者へ届ける想いとは?
石田:最後に、次に100年へ変えるもの、変えないもの。会社のコアになっていく部分を伺えますか。
牛田:これまでの経験や実績を活かし、噴霧器の製造を行っていこうと思います。さらにどんどんと進化していく衛生害虫に対応していく技術を磨いていきたいです。
朝岡:100年先の牛田噴霧器工場はどうなっていますかね。
牛田:もしかしたら、巨大化しているかも知れませんね。今まで作ってきたものは変えられません。しかし、これからを作っていくのは、私であり、後の代の人間たちなので、その時代ごとにどんなものが必要なのかを考えなくてはいけないですね。
朝岡:現在、製造から販売、実際の駆除まで行っている。将来この形は続くと思いますか。
牛田:続いて欲しいです。やはり、現場を見て実際に使ってみないと分からないと思いますね。だからこそ、開発と施工を同時にすることは必要ですね。これは残して欲しいですね。
朝岡:100年後の害虫は凄く進化してそうですね。
牛田:今でさえ、蚊が菌を媒介するということがあるので、とてつもない害虫が出てくるかもしれないですね。暖かいと虫が成長します。日本も温暖化で暖かくなり、ゴキブリが100倍サイズにみたいなこともあり得ます。一番怖いのは人間に影響を与えてくる二次被害ですね。
石田:2020年東京オリンピックで多くの外国人の方がこられますが、そうなると害虫も入ってくる可能性も高くなるのですか。
牛田:おっしゃる通りです。外来種は今でさえ増えています。入れないように防ぐということも考えられるのですが、入ってしまった際、私たちがどのような対処をするか本当に重要になると思います。さらに、2020年に向けて建物をエコ化しようという動きがあります。実は、私たちはそれを脅威だと考えています。というのも、新しい建材やコンクリートは水分を含んでいます。使っていくうちに、水が出てきて、湿気、結露さらにはカビを発生させます。カビを食べにくる害虫もいます。良かれと思ったことが逆に2次災害を生む可能性が在るので、気を付けていかなくてはいけないですね。