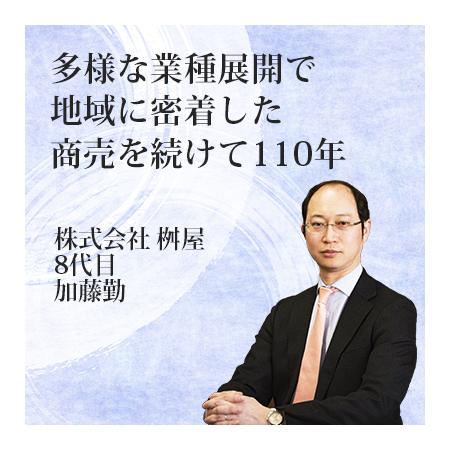
- 2020.10.02
桝屋 〜多様な業種展開で地域に密着して110年
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは株式会社桝屋。8代目代表 加藤勤。
1907年、株式会社桝屋の前身となる、合資会社桝屋商会が誕生し、米穀精米、製粉、食品、肥料・飼料、石油製品、セメントなど、卸会社として、三多摩地域に事業を展開してきた。その後、1947年に現在の「株式会社桝屋」に商号変更し、1958年のスーパーマーケット「マルフジフードセンター」を開店以後、時代の変化に対応しながら、卸売業から小売・サービス業に事業転換を果たし現在も「お客さまに信頼され、満足していただける経営」を信条に、地域密着で日々のくらしに必要な商品の販売とサービスを提供しているのだ。
今回はそんな桝屋の8代目代表、加藤勤の言葉から、先代達が下した決断、語り継がれる物語を紐解き、桝屋がもつ「長寿企業の知恵」に迫る!
石田:今回のゲストは、株式会社代表取締役社長 加藤勤(8代目)さんです。よろしくお願い致します。
一同:宜しくお願いいたします。
朝岡:桝屋さんは様々な事業なさっているようですが、具体的にどのような事業内容ですか。
加藤:例えば、不動産業や食品スーパー、カーディーラー、あとガソリンスタンド、書店などですね。
決断 ~ターニングポイント~
続いてのテーマは決断。
まずは桝屋にとってのターニングポイント。これまでに訪れた苦境、それらを乗り越えた術とは。
石田:まずは桝屋さんにとっての転機・ターニングポイントをお伺いできますか。
加藤:4代目の社長 加藤裕一。私の叔父にあたるのですが、社長在任中に48歳で急に亡くなられました。桝屋の社長で、グループの中核で、急なことでしたので、私どもの歴史の中でもかなりのピンチだったと思います。私は当時小学2年生でしたが、家中大騒ぎしていたのを覚えていますね。
朝岡:急に亡くなられたとのことで、その時どのようにして乗り越えたのですか。
加藤:その時は私の父ですとか、叔父達。ちょうど30代、40代でした。私の祖父もいたので、みんなで補って、事業を継続させていったと聞いています。
朝岡:家族が一致団結していくというのが、桝屋さんのカラーみたですね。
加藤:そうですね。家族一致団結はピンチの時、より一層大事だなと感じています。
石田:代によって、様々な事業をされているのですよね。
加藤:私の叔父が急逝し、次が私の父だったのですが、配送参拝事業や本屋、カラオケ事業などを始めました。次が私の叔父ですが、その時、不動産業を本格的に始めました。次に歳は離れていますが、私のいとこになります。その時はカーディーラーや飲食店事業を始めました。
朝岡:100年を越える企業様で、代が変わる頃にビジネスを新しくしていくというのは珍しいですね。
加藤:そうですね。珍しいですかね
朝岡:在任する社長がこれをしたいと思ったものをしていいのですか。
加藤:みんな中々個性が強いものですから。よく言えば起業家と言えますね。アントレプレナーですかね。
続いて、加藤勤にとってのターニングポイント。
石田:ご自身にとってのターニングポイントをお伺いできますでしょうか。
加藤:一番は書店の事業を平成15年に引き継ぎました。その時会社としては大変な状況で、赤字も大きく出している状況でした。不採算店を閉めるとか、取引先を変えるなどをしました。受け継いだときは9店舗あったのですが、一旦6店舗くらいになりました。そこから黒字に転換することができ、最大12店舗まで大きくなりました。現在は10店舗で運営しています。書店事業の再生をできたということはいい経験であり、自信になっています。
朝岡:各代表が広げていくので、引き継いだときに、引かなきゃいけないことも多々あるような気もするのですが。
加藤:そうですね。本屋は上手くいった例で、父が始めたカラオケ事業というのがありました。それも引き継いだのですが、ちょうどリーマンショックがあり、競合も多くでてきて、最終的に撤退することがありました。痛みもありますが、一つの大きな経験にはなりました。引くときは引かなくてはいけないなと感じましたね。
石田:バランスを見て、どのタイミングで引くかなど難しそうですね。
加藤:そうですね。気持ちとしてはいつまでも続けて行きたいですが、どこかのタイミングかで決断しないと、傷がより大きくなってしまいますので。
石田:そのような経験を乗り越えて学ばれたことはありますか。
加藤:そうですね。事業を支えるのは人だなと思いましたね。カラオケの事業は引き継いだときの状態は、本屋の方がよっぽど厳しかったです。それを支えていく人材が十分育っていなくて、競合が出てきたときに勝てなかったりしたので、事業を支えていく上で人が大事で、人が育っていないと成功する可能性があっても、上手くいかないケースが多いですよね。
朝岡:加藤さんの場合、幼少期からお前は何代目だよといわれるのですか。
加藤:私は実は次男坊です。長男は別にいるのですが、現在別の仕事をしています。結果的に私が継いでいます。実は私の父も次男坊で、流れからすると私は傍流の方です。なので、必ず継ぎなさいみたいなプレッシャーはなかったですね。
石田:そうなると、継がれる前は何か他にしたいことなどあったのですか。
加藤:もともと海外に興味があったので、外交官試験受けたりしたこともありましたね。
朝岡:実際に継ぐとなった際は、任命されたのか。立候補したのか。どうだったのですか。
加藤:親の方から声かけがあったのですが。私としても、学生のときに台湾や香港など現地の大学生と交流する機会がありまして、日本だと公務員になるとか、大企業に入るというのが人生のゴールみたいに言われますが、海外に行くと自分で事業を起こすことの方がステータスというのを肌で感じました。その時から経営というのに興味がありました。
朝岡:もともと海外に興味があって、結果的に海外でも仕事が出来ていいですね。
加藤:計画的にしようとしたわけではなく、人とのご縁や、めぐりあわせでそうなりました。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
言霊。心に刻む言葉と想い。
強い思いと信念が込められた言葉には魂が宿り人の人生に大きな影響を与える。
8代目代表加藤勤が先代や家族から受けとった想いとは。
石田:続いては言霊ということで、幼少期におじい様、おばあ様から言われた印象的な言葉などありますか。
加藤:子供のとき、スーパーや書店を親がやっていましたので、友達からしたらスーパーでお菓子食べ放題、本屋で漫画読み放題でいいなと言われますが。実際そんなことは全くなく、スーパーであっても、本屋であってもお金を払って買っていました。お店のものは公のものであると教えられてきましたね。会社運営する上で、会社のものは私有のものではないと。
朝岡:お店での接し方や商品の扱い方を日頃から教わっていたのですね。 加藤:背中を見て育つではないですけど、自然と親の行動の中から得ていたかもしれないですね。
続いて8代目加藤勤が現在胸に刻む言葉。
石田:現在、ご自身が胸に刻むお言葉などありますか。
加藤:私、中国語が好きでして、中国語の本書いたりしているのですが。毛沢東が言ったという説もある、中国語の言葉なのですが。『吃水不忘挖井人』これはどのような意味かというと、水を飲むときに井戸を掘った人のことを忘れてはいけない。先人の努力を常に忘れるなという言葉です。
石田:発音が流石ですね。
加藤:ありがとうございます。この言葉は自戒も込めて大事にしています。
朝岡:先人の努力を忘れてはいけないということですね。
加藤:特に私みたいな先祖から受け継いだ事業をやっている人間は忘れがちになってしまいますので。
石田:中国語のマスターする方法などの本を出版しているのですね。
加藤:はい。『中国語が一週間でいとも簡単に話せるようになる本』っていう本ですね。
朝岡:また、売れそうなタイトルの本ですね。
加藤:6年前に出版したのですが、お陰様でそろそろ2万部に到達しそうです。
朝岡:2万部も売れているんですか!!
加藤:中国語の本としてはベストセラーな方かと。
朝岡:ビジネスでもそうですが、中国の方と交流しなくてはいけない機会が増えていますよね。ただ英語と比べて、まだ浸透していなく、うまくその隙間を埋める本ですね。
加藤:中国語勉強する方は増えていると思います。ただ、中国語好きで、本当に話せる方は少ないですね。大学生なども今、第二外国語で中国語勉強する方は増えていますね。その中でもっと簡単に、ハードル低く話せるようになる方法があるのではないかと、この本に書かせていただきました。
石田:加藤さんは長寿企業のリーダーでもありまして、社員の方とコミュニケーションするのに心がけていることありますか。
加藤:そうですね。こちらから声をかけ、歩み寄ることが大事かなと。なかなか出来ていないですが。やはり社員からすると話しかけ辛いと見られがちなので、歩み寄ることを心がけています。
貢献 ~地域、業界との絆~
地域や業界との絆。
長寿企業にとってなくてはならないもの、それは地域との絆。
桝屋が行っている地域貢献そして業界での取り組みとは。
石田:地域や業界との絆ということで、地域で取り組んでいらっしゃること、社会貢献されていることなどありますか。
加藤:地域のお祭りで、私どもの会社は福生というところ発祥なので、福生の七夕祭りという8月に民謡パレードがあります。2時間くらいかけて町を練り歩きます。駅前のメイン通りが一番の見せ場です。私どものグループは私を含めて毎年参加しています。私も踊っています。
朝岡:楽しそうですね。お祭りだと堅く地域貢献活動というより一般の方と一緒に出来るのはいいですよね。
加藤:スーパーの丸藤の方でも、福生七夕祭りに協賛していて、ミス織姫コンテストというものを毎年やっています。いわゆるミスコンテストで、ミス織姫に選ばれると1年間福生の広報活動をして頂くことになります。
朝岡:はじめ伺った時、桝屋さんの場合は地域に密着する企業と事業内容をお伺いしましたが、地域密着が大事だからこそ、こういった形で参加されるんですね。
加藤:あと、今丸藤でやっているのは、レシートを集めて、その集まった金額で、地域の児童館にお金でなくて、児童館が欲しいというものを寄付するというのをやっています。卓球台とか、児童館の子供たちが本当に欲しいものを寄付しています。地域の新聞にも取り上げていただいて注目いただいている活動であります。
石田:地域の皆さんと溶け込んでいる様子が目に浮かぶのですが、業界との取り組みはございますか。
加藤:スーパーについて言うと、CGCという小さいスーパーが集まって、大手のスーパーに対抗しようということで出来た、ボランタリーチェーンという、同じ商品を一緒に仕入れて、大きなスーパーは沢山仕入れますので、集まることによって同じくらいの量を仕入れて、安売りに対抗できるようにしようと、もう40年近く取り組んでいます。全国規模の組織ですので、普通スーパー同士で交流しても、競合同士なので、自分たちのことは教えづらいですが、地域から離れることで腹を割って話せますね。
朝岡:このような取り組みを始めたきっかけは何ですか。
加藤:当時はセイユ―さんとか、東急ストアさんとかができ始めたころで、あれだけの鉄道の資本で大量に出店をされて、ちょうど首都圏のスーパーはみんな危機感をもっていました。早く亡くなった加藤裕一が社長をやっていたとき、有志のスーパーで集まって、そのような団体を作りました。
朝岡:ネットを結ぶことで、急に出てきた鉄道系のスーパーに、ある種対等に渡り合ったんですね。
加藤:今、全国に和が広がって、3兆円の規模になっています。
伝燈 ~受け継がれる伝統~
受け継がれる伝統。先代から受け継がれている書物や品、そこに隠された想いに迫る!
石田:続いて、加藤さんも今8代目ですけど、代々受け継がれてきた書物などありますか?
加藤:代々受け継がれているものとしては、焼き印です。鉄の棒の先に桝屋のマークが入っています。昔はお米とかを売っていたのですが、それが桝屋の商品とわかるように、焼き印を押していました。それが今でも残っていて、私どもの屋号の桝屋の原点の形として受け継がれています。
朝岡:100年を越えますと、そのほかに印刷物とか本があったりしますか。
加藤:ちょうど私の先代のころに桝屋の創業100年を迎えました。それを記念して100年の沿革の本を作りました。昔のチラシや、従業員の様子などの写真を沢山交えて、あと、制作の方を地域の郷土歴史を研究されている方にお願いしたこともあって、地域郷土の歴史流れと一緒に桝屋の歴史の流れを残していただいている本があります。
朝岡:会社の歴史と地域の歴史が両方わかるような形なのですね。
加藤:制作するときに丸藤のお客さんにも公募しまして、昔の写真ですとか、昔のもので丸藤や桝屋のマークが残っているものなど公募して、それを百年史の方にも載せています。
朝岡:やはり100年超えているとお客様も世代を超えて、代々桝屋さんとか、丸藤でお買い物して育っているというお客さんいっぱいいそうですね。
加藤:あと従業員の方も大事に取っていらっしゃる方がいますね。
朝岡:ネットを結ぶことで、急に出てきた鉄道系のスーパーに、ある種対等に渡り合ったんですね。
石田:一冊そのような雑誌があると、今の人もそうですけど、これからの人も、その冊子を見ることによって、桝屋さんの歴史が分かりますね。
朝岡:本当に色々なことを伺うたびに、地域とのつながりというのが浮かび上がってきますね。
NEXT100 ~時代を超える術~
NEXT100時代を超える術。革新を続け、100年先にも継承すべき核となるものは。
桝屋の8代目加藤勤が次代へ届ける長寿企業が持つ智慧とは。
石田:最後に次の100年に向けて、変えるもの、変えないもの。この先御社にとってコアになる部分をお伺いできますか。
加藤:100年というと本当に長い時間で、これから100年後の未来というのは丸っきり変ってしまっているのかなと思いますが、段々寿命の方も延びて100歳まで生きるのが当たり前の時代になっていくでしょうし、インターネットもIoTなどドンドン進んで、人の働き方など大きく変わっていくのかなと思いますが、その中でも、人の本性というのは変わらないのかなと思います。
人間の歴史というのは、明治とか江戸時代とかずっと続いていますけど、その時の小説とか歌舞伎を見ても、人間というのは結構同じで、恋愛したり、欲得で動いたり、同じことをずっと繰り返しながら歴史を辿っているのかなと思います。100年後にしてもても人間の本性はやっぱり変わらない。やはり、欲もあれば、僻みとかがある。
100年後の子孫にも私どもが伝えられた通り、兄弟仲良く豊かな生活を過ごすことが大事だということを一番伝えるべきことかなと思います。
朝岡:事業の中身としては、やはり不動産を柱にして、次の代表の展開したい事業をその代、その代で行っていくというのは変わらなさそうですか。
加藤:そうですね。事業が何をやっているかというと、けして同じということはないと思います。今回介護の事業始めましたけど、それがグループのインフラになればいいなと思っていて、今、私どもスーパーやって、そこで食品売っていますが、介護の事業はお迎えにあがるわけですよね、その中で重たいお米とか、お水とか買っていただければ、買う方も楽に買えるというような。今私どもホンダの車売っていますけど、10年20年したら、ホンダも介護用ロボットを作るのではと思っています。そうすると介護を利用していただいている方に介護用ロボットを売るというようなことが、そんなに遠い未来ではなくて、実現していくのではと、夢を抱いています。
朝岡:今やっているお仕事の中で並列なものを、介護を中心にネットワークを築いていくみたいなことをお考えなのですね。
加藤:そうですね。
株式会社桝屋、8代目代表加藤勤。
時代が変わっても人間の本性は変わらない。人は歴史から学び、先人たちと同じような道をたどって行くものである。
受け継がれてきた地域との絆を第一に、今後も事業を行ってほしい、この想いは100年先の後継者たちへ受け継がれていくだろう。最後に文字アーティスト平井省吾が株式会社桝屋8代目代表加藤勤の言葉から感じ取った想いメッセージを書に綴る!
「正直、豊かさ」正直な仕事は桝に新たな水が入り溢れる豊かさに繋がっていく。