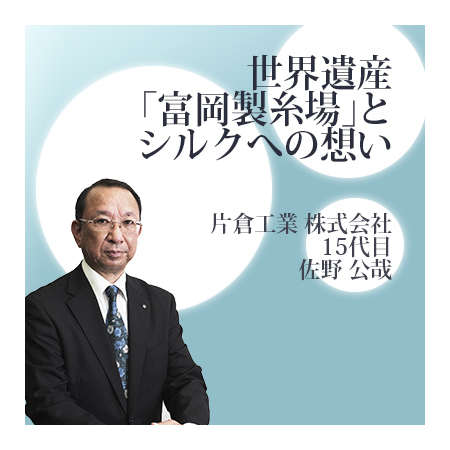
- 2020.10.03
片倉工業 〜世界遺産「富岡製糸場」とシルクへの想い~
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは、片倉工業15代目、佐野 公哉。片倉工業は製糸を祖業とし、1873年に創業。
シルクを通して、日本の近代産業の発展に貢献。
社会情勢の変化とともに、140年以上もの歴史と伝統の中で培ってきた進取の精神のもと、製糸から派生した繊維事業、医薬品事業、機械関連事業、不動産事業、人々の暮らしに寄り添い、現在も多角的に事業展開している。
今回は、そんな片倉工業の15代目佐野 公哉の言葉から、事業継続の秘訣その裏に隠された物語に迫る!
石田:本日のゲストは片倉工業株式会社、代表取締役社長、佐野公哉さんです。宜しくお願い致します。
佐野:宜しくお願い致します。
朝岡:長い歴史のある片倉工業ですが、現在の事業の内容を簡単に教えていただけますか。
佐野:現在は、祖業の繊維と医薬品、機械関係、不動産、この事業に加えまして、新規の事業を加えています。
石田:佐野様は今、何代目でいらっしゃるんですか。
佐野:私は15代目の社長でございます。
朝岡:はあ~、15代目。
石田:そしてこちらに、片倉工業の製品をお持ちいただきました。ご説明いただけますか。
佐野:はい。数有る事業の中でもですね、特に当社の祖業に関係あるシルクの商品でございますが、プレミアシルクでございます。どうぞ、お手に取ってご覧ください。新ブランドの「Katakura Silk」でございます。
石田:すごい、柔らかいですねー。
佐野:当社のシルク製品で、毎日心地よく過ごしていただきたいということでございます。伝統的なシルクの良さを知っていただくということで、良いものを身につけて頂くことの気分の良さ、それからゴージャスな気分を感じて頂ければと思います。
朝岡:これね、日本の絹と言ったらね、昔は世界の最高級品でしたもんね。
佐野:国産のシルクでございますので、縫製も仕上げまで国内でやっております。
朝岡:高級品ですねー。
佐野:そして、こちらはスキンケア化粧品でございます。クレンジングクリーム、化粧品、オールインワンジェル、洗顔石鹸ですね。こちら、私共の研究所でミツバチを飼っておりまして、ミツバチの取ったハチミツ自体を使って、シルクの元々の成分である「セリシン」を原料といたしまして、ハチミツとセリシンを原料とした絹水という希少化粧品でございます。
石田:お名前からして凄く保湿力が高そうですよねー。
佐野:大変好評でございます、是非お試しください。
石田:そしてその他にも、不動産業ですとか、あと機械関連事業とかも出されてるんですよね。
佐野:不動産事業はですね、元々製糸工場を蚕種製造所に関連する事業所が全国にございましたので、その工場跡地を利用するということでですね、佐野:ショッピングモールですとか、佐野:介護施設等を運営しております。不動産事業の中でもっとも大きいところは、埼玉県のさいたま新都心の駅前にあります、コクーン、コクーンシティですね。
朝岡:あそこは片倉工業さんが。
佐野:はい、そうです。大宮製糸場の跡地になります。
朝岡:製糸工場の跡地だったんですか。
石田:それだけ広い敷地があったということですねー。
佐野:あとは機械関連のことなんですけど、元々製糸工場の中でですね、製糸機械、糸を紡ぐ機械を自社で生産しておりました。それをルーツに持ちます機械関連。中でも農業機械ですとか、消防自動車を作っています。消防自動車は、国内でもNO.2のシェアを誇っています。
朝岡:あら、消防車のシェアNO.2、知らなかったなー。
佐野:これもですね、やはり意外性があるんですけども、私供の製糸工場からの発生でございます。
石田:やー、ビックリですねー。
朝岡:生糸をね、作るという結びつき、それがまあもともとのアレですけれども、それが強みというのは改めて感じますかねえ。
佐野:そうですね、あの、それぞれの事業が製糸工場から派生した事業ですので、そういった点では全て身内のようなグループを形成しております。
石田:そしてですね、社長のゲン担ぎも、やはりシルクと伺ったのですが、今日も何か身につけていらっしゃいますか。
佐野:そうですね、少しお見せできませんけども上も下もシルクです。かつてはブランドライセンス業に力を入れていた時代もありまして、その時代はこの上から下までシューズまでのブランドを持っておりましたので、全部身に纏うものが自社の製品、ないしは自社のブランドでした。全部身にまとうものが自社の製品ないしは自社のブランドで身に着けれた。今はライセンス業を弱くしてますので、シルクの下着が私の勝負下着です(笑)
朝岡:勝負下着!これがねー、本当の洒落者はね、アンダーウェアに凝るといいますからね。
石田:その通りですよー
朝岡:なるほどー。意外だったなー。
ここからは、各テーマを元に、片倉工業15代目、佐野公哉の言葉から歴史と伝統の裏に隠された「物語」、
片倉工業が誇る「長寿企業の知恵」に迫る。
最初のテーマは、「創業の精神」
創業者の想いを紐解き、現在に至るまでの経緯を、片倉工業の15代目、佐野 公哉(さの きみや)が語る。
石田:創業の精神ということでまずは片倉工業さんの歴史や現在に至るまでの経緯を伺えますでしょうか。
佐野:はい。1873年明治6年に長野県の諏訪郡川岸村、現在の岡谷市で10人取の座繰(ざぐり)という製糸を始めたわけです。これが明治5年ですから富岡製糸場が開業して翌年です。
それから1878年明治11年に6月、初代の片倉兼太郎が川岸村に洋式の器械製糸工場垣外工場を開設いたしました。明治28年には製糸事業の拡大に伴いまして片倉組を組織いたしました。同時に、東京京橋にも支店を開設することになります。
1919年、大正8年には朝鮮、現在の韓国の大邱に製糸工場を開設して、1924年大正13年にはニューヨークに支店を開設していくという形で世界に目を向けていったわけですね。
1928年、昭和3年には御法川式多条繰糸機という自動的に糸を引き上げてですね、絹糸を作っていくという機械を独占導入してですね、高級生糸の片倉ミノリカワ・ローシルクという、これが当初のブランドでしたけれども世界的評価を得るようになりまして昭和初期のピーク時には日本の輸出の約4割をシルクで占めて、そのうちの2割を片倉がシェアを持っていたということで、実績はトップだったと聞いております。
朝岡:戦前のね、戦前の日本の生糸ってのはね輸出品の柱でしたからねー。
佐野:はい。外貨獲得のためということで日本の産業の中心だったわけですね。
朝岡:大正時代から海外にこうやって支店を設けられているわけですけれども、そもそも絹というものに目を付けたっていうその先見の目っていうのはどのあたりにあったんですかね。
佐野:日本のシルクは江戸時代にはまだ製品が均一ではなかったわけです。そこで、まだ江戸時代には、(シルクは)輸入に頼っていました。中国とかヨーロッパの輸入に頼っていました。そこで明治時代になって輸出推奨策の一つとしてシルクが注目されて、国策としてフランスから技術者を招いて、それから富岡の製糸場が操業していくわけです。
富岡製糸場は、2014年に世界遺産になったわけですけども、富岡市に寄贈するまではですね、私共が66年富岡製糸場を保有しておりました。その66年のうちの後の18年は、工場の操業を停止してから保存管理だけになったわけですけれども、それ以前はですね、私共が最も長い期間富岡製糸場を本当の生糸を紡ぐ工場として使っていたわけですね。
朝岡:片倉工業は代々創業者一族の経営でやってらっしゃったのですか。
佐野:第二次世界大戦までは片倉一族が経営をしておりました。で、終戦と同時に財閥解体、で一族から離れてったわけですね。
石田:そんな片倉工業さんのですね、家訓や理念を伺えますでしょうか。
佐野:片倉家の家憲10か条というものがあります。
朝岡:家憲というのは家の憲法…
佐野:憲法ですね。
朝岡:それで「家憲」ですよね。10カ条は、もともとはその片倉家の家憲というのが10か条あるんですか。
佐野:ええ、10か条ございます。
でその家憲をですね、現在会社の中では家憲としては使っておりませんけれども、その中に重要なところが私の中でありまして、4番目にですね「家庭は質素に、事業は進取的たること」。第10番目に「雇人を優遇し、一家族をもってみること」。これらが私にとっても家憲の10か条の中でわたくしが重要視しているところでございます。
朝岡:これは実際働いている方々に浸透させるには何か工夫をしていらっしゃることはあるんですか?会社で。
佐野:一般的にやっていることと同じだと思いますが、社員手帳への掲載ですとか、各会議室の部屋への掲示ですとか、会議室にも当然ございます。社員向けのこういった小型の卓上カレンダーに、その理念を入れたカレンダーをみなさんに使っていただいたりですね。
あと新しく新入社員で入社しますと富岡製糸場と私共シルク、熊谷にシルク記念館という施設があるんですけれども、当然それは入社したら見てもらうんですけど。片倉家の創業の地岡谷にですね、行って初代の生家を見てもらって、お掃除もしてもらって創業の精神に触れてもらうというところから会社に馴染んでもらいたいなと思っています。
朝岡:やっぱりこれだけ歴史が出てくるとね、そもそもどういう志と気持ちでね、仕事を始めたのかと。少し遠いところになりがちですからね、そこに新入社員の皆さん行って、創業の地へ行って実感してもらうということですか。
石田:実際に社員としてもう働いていらっしゃる方とコミュニケーション、これもいろいろ工夫なさっているとお聞きしましたが、何か具体的にやっていらっしゃることを教えていただいてもよろしいでしょうか。
佐野:ランチミーティングというのをやっていまして、これは先代の社長から引き継いでいるんですけれども。社員、課長以下の社員を絶対に4人か5人呼んで、普段持ってきているお弁当でいいんですけれども、会議室の一つをランチミーティング用の部屋といたしましてそちらで会議をしながら、皆さんの意見を聞きながら、私の想いを伝えながら、っていうことをやっています。
そこで普段直接私と話をしていただけることはないんで、そういった点では直接話ができるということと、普段思っていることが、なかなか実現できないことでも直接社長に話せたということが大事にしていますので。そう言った点ではいい機会だなと思っています。
決断 ~ターニングポイント~
続いてのテーマは「決断 ターニングポイント」
片倉工業の発展と共に訪れた苦境、そして、それらを乗り越えるべく下した決断を、片倉工業15代目佐野公哉が語る
石田:続いては、決断・ターニングポイントということで、まずは会社にとっての転機、ターニングポイントを伺えますか?
佐野:会社のターニングポイントは、終戦後に起きた事業の転換です。1938年にアメリカで発明されたナイロンの工業化ですね。これによって化学繊維が登場してきます。
朝岡:あー化学繊維は、いわゆる化繊が入ってきてね、ずいぶんその地図が変わったっていうか。
石田:そこをどう乗り越えてこられたんですか。
佐野:それはですね、第二の創業期とも呼べます、経営多角化への取り組みでございます。例えば、繊維事業の中でも肌着への転換、シルクから肌着への工場転換ですとか、セーター、パンスト、ブラウス等々ですね。こういった事業への転換をしていったわけですね。
それから、不動産の開発も後にございますね。小売業へも直接、ホームセンター事業にも入ってきました。それまで製糸工場一辺倒だったところがそれだけ生産が減っていくわけですから、時代に合った形で展開していかなければならなかったということですね。
朝岡:もうまさに進取の、新しいのを取り入れることがどうしようもない…そうしなきゃ生きていけないっていう
佐野:その通りです。
朝岡:そういうことになっちゃったんですね。それが一つ、多角化の大きな理由ということでよろしいんでしょうかね。
佐野:そうですね。家憲にもあります通り、進取果敢な精神があったことだと思います。一見バラバラな事業に進出しているように見えますが、原点はシルクの工場でありまして、その時代その時代に合わせた事業に進出していくことが、片倉の今まで生きてきた長寿企業のDNAと思っております。
石田:一方で社長にとってのターニングポイントはございますか。
佐野:私にとりましては、現在スタートいたしました、新中期経営計画「カタクラ2021」の発表であります。かつては、片倉工業は前例主義の経営でありました。そこから脱却してですね、これまでの方針を受けつつ構造改革、重点戦略分野を定めた計画を立案していくことで、当社以外のグループ会社の中堅層も計画に、立案に巻き込んでですね、将来ありたい姿を議論して、5年間の計画へ落とし込んでいったものであります。
朝岡:この新中期経営計画「カタクラ2021」というのは具体的には説明してもらうとどういったものなんですか。
佐野:到達目標は、愛される200年企業の礎ができていることとしておりますが、既存事業の成長と構造改革をベースに重点戦略分野であります「介護福祉・健康」、「アグリ・環境」、「防災・安全」、「高付加価値素材」、「さいたま新都心エリア」での新事業。この5つの分野にですね、各セグメントの経営使命を持ち寄りまして、他社との業務提携やM&Aを積極的に活用しながらグループの柱となる事業を創出して目指していくということでございます。
朝岡:やっぱり社長、佐野さんが入社なさった当時とは、いわゆる繊維業界というのは環境というのは激変していると見ているわけですよね。
佐野:そうです。
朝岡:それを踏まえてこれからの片倉をこうするというのが今の計画。
佐野:そうですね、繊維産業自体が、国内から韓国へ中国へ、ASEANへというふうに生産基地が移ってきましたので、そういった点では国内の繊維産業はだんだん変化をしてこざるをえなかったということですね
石田:時代の波に乗ると言いますか、対応する上で心がけていることはどういったことがございますでしょう。
佐野:前例主義ですね。私たちは、どうしても長く同じ仕事をしてきた会社としまして、前例主義の部分がありますので、承継していかなければいけないもの、変えていかなければいけないもの、捨てなければいけないもの。こういったものをですね、見分けて、切り分けていくということ。これが常に心がけていることですね。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
言魂。心に刻む、言葉と想い、強い想いと信念が込められた言葉には魂が宿り、
人の人生に大きな影響を与える。佐野公哉が先代や家族、恩師から受け取った言葉、その裏に隠された想い・物語とは?
佐野:私は大学を卒業して地元に帰らなければいけないという思いがありましたけど、本当は東京のこの場所で仕事をしたかったんですけれども。父に帰らなければいけないか確認しましたら、自分たちが、父は戦争末期の人ですので、若い時に戦争に行くことを考えたら日本国内にいて世の中の役に立つことができるのであれば、家を選ぶのではなくて、自分のやりたいことをやりなさいと。そう言われたことが、今片倉工業の中で仕事をさせてもらっているということで、父には感謝をしています。
朝岡:なるほど。自分がやりたい方向に行けと、いうことですか。
佐野:一般的によく使われることだと思うんですけど、農家の長男でしたからある意味では一族をまとめなければいけないという側面もありまして、そのことを大学時代もずっと心にどうしたらいいかという思いがありましたので、父がそういう風に言ってくれたことで吹っ切れて頑張れるようになったという感じですね。
朝岡:そうですか。ご自身の環境からの体験ですと大きいですよね。
石田:ところで、今現在社長の心に刻んでいる言葉はございますか。
佐野:「進取果敢」という言葉でございます。四文字熟語でございますが、一貫してぶれないで貫こうと、これからも貫こうと思っております。
朝岡:片倉家の家憲の一つにあった「進取」にとてもよく似ているわけですけれども前に進みながら新しいものを取り入れていくということがある種自分の生き方、会社の生き方ということは信念になっているわけですね。
佐野:そうですね。
石田:ところで、社長ご自身はですね、社長に就任されると思ってましたか。
佐野:いえいえ、もう全然(笑)。常務の時に、次の社長ということでご指名を受けたときにですね、本当に驚いたくらいですから。それまで社長になるための帝王学を受けておりませんし、私はもともとサービス部門で、お客様に接する仕事をしてましたから、本部中枢の仕事っていうのは入ったのは50歳を過ぎた後でしたから、そういった点では本当に驚きました。
朝岡:でもね、大体あれですよ、社長になろうと思ってなった方っていうのは非常に少ないと思いますよ。と思うんですけど、どうです?佐野さん。他の社長をご覧になってて。
佐野:それは、一つ一つ与えられた任務をこなしていくという連続だと思うんですよね。自分の望むところにばかし配属はなりませんよね。配属された場所で、自分の与えられた使命はきちっと理解して、勤め上げられるか成果を出すか、ということの繰り返しだと思うんですね。
石田:そこが評価されて大きな信頼を集められたということでしょうね。
朝岡:その先に、自分の思わぬところから、会社の上の方とかよく見てて「はい、君社長」ということが多いような気がいたしますね。
貢献 ~地域、業界との絆~
地域や業界との絆。長寿企業にとってかかせないもの…それは…地域との関わり。片倉工業が行っている社会貢献、地域との取り組みとは?
石田:現在地域での貢献活動など、何か取り組んでらっしゃることはございますか。
佐野:一つは埼玉県のさいたま市にあります、さいたま新都心駅前にございます、コクーンシティでございます。さいたま市とは、旧大宮市なんですけども、製糸工場に進出してから100年余りの乾繭がございます。地域の歴史とともに、工場が歩んできた土地でございますので、現在は商業施設の「コクーンシティ」という名前を付けておりますけれども、このコクーンシティを通じて地域に貢献して、さらに環境への取り組みをしています。
「SEGE2016都市のオアシス」という商業施設として認定もされておりますし、今後もさらに地元との関係を深くしていきたいと思っております。
朝岡:コクーンていうのは、片倉工業あるいは佐野さんとも大変深い関わりがあると伺ったんですけれども、そのあたり、ちょっと説明してもらえますか。
佐野:片倉工業の創業でございます、製糸工場ですね、製糸の繭という意味です、「コクーン」というのは。それから取って、コクーンと命名しました。現在それが拡大して、一大商業エリアのコクーンシティとして成長したと。このエリアは製糸工場の跡地でございますが、そのあとにホームセンターですとかゴルフ練習場ですとか遊園地ですとか、前の形のショッピングセンター、そういう施設になって、30年くらいたった後に今の形に変化させてったわけです。
私も一番最初は、街づくりに参加したかったですね。片倉工業が工場も閉鎖して広大な土地が空きますので、またその土地を活用してその地域地域にあった、時代に合った求められる施設にしていきたいという思いがあったんですけれど。私がそういう事業につけたのは入社して30年後だったというわけですねえ。でもそういうところに就けたところが大変その時には、やっと自分が片倉工業で実現できる仕事に就けたと思ったときはいろいろそれまで思い描いていた沢山のことをですね、実現しようという思いで仕事に取り組みましたね。
朝岡:繭から出てね、いろいろこう蚕になってみたいな。変化のね、シンボルですよ、コクーンは。
佐野:地域とも親しく、ずっと持ちつ持たれつで来れているというのは、地元のお祭り氷川神社のお祭りに町内神輿を寄進しています。そのおみこしが町内を、片倉を中心にして盛り上げていこうという気持ちを町内の方々にも思っていただいておりますし、私も前のコクーンシティのできる前の施設、大宮片倉パークの支配人をさせてもらったときから、それまで大宮の駅まで神輿が行っていたわけですね。ですがせっかくさいたま新都心の駅ができてコクーンができたんだから、このエリア内でお神輿を担ごうよ。町会の会長さんですとかお神輿の会を説得して理解してもらってお願いをして。今はコクーンから出発して、さいたま新都心の駅周辺を登用しているということで大変思い出深いことですね。
朝岡:そういうことですか。
石田:他にも地域との交流はございますか。
佐野:群馬県の富岡市ですね。これはユネスコの世界遺産に登録されておりますのでいろいろな情報で伝えさせてもらっていると思いますが1939年から2005年まで66年間保有をしておりました。民間としては最後のオーナーで務めたわけですけれども富岡市に寄贈するまでの最後の18年間は建物の保全管理をしてきました。
現在も2010年以降富岡市に(片倉工業の)株主優待の一つとして富岡製糸場への寄付というのを選択できるようになっております。株主さんが優待の中のチョイスしたものの中に、富岡市への寄付を選んだ方々の資金は私どもがお預かりして富岡市に毎年寄付させていただいております。それは私どもからではなく株主様から富岡市へ、という風にしております。
朝岡:そうですか。やっぱり世界遺産の時にまた一気に脚光を浴びましたけれどもこれはもともと片倉工業が工場としてお使いになっていたというところってのはね。
佐野:実際に使っていたものがそのまま残されているっていうのが大事なところで。
朝岡:そうですよね。
佐野:明治政府から、ずっと工場に携わった先人たちのどれだけ努力されたかという。私たちにしてみれば、畏怖の念があるから大事に私ども保存して世界遺産に結びづけたというわけですね。
伝燈 ~受け継がれる伝統~
受け継がれる伝統。創業以来、代々受け継がれている書物や品物・・・。そこに隠された想い、物語とは・・・?
石田:続いて、片倉工業さんで代々受け継がれているもの、品というものはございますか。
佐野:これはその一部なんですけれども、片倉工業の商標でございます。これは海外に出すときに使われていたものですけれど、
石田:この方が初代…
佐野:はい。その中にですね、当時使われていた商標の、生糸の商標がございます。その生糸の商標がたくさんあるんですけれども、それが私にとっても会社にとっても宝ですね。
朝岡:日本の輸出製品の看板ですというのが商標から感じますね。
佐野:明治の初期にはですね、まだまだ製品が均一化されていなかったものですから、片倉の商標が付いたものが安定したいい製品であると証明されておりましたので、そういった点である意味では、金看板だったということが言えるかと思います。
これ自身見ていくと衣装的にも素晴らしいのがあるんですよね。戦争中は…またその時代に合ったデザインがありましてですね。
石田:日本らしさが出てますね。侍の絵ですとか…
朝岡:デザインの歴史としてもすごく興味深いですね。
佐野:そうなんです。個人的にもですね、時間ができたらこれを整理してですね、一冊の本にしたいと考えております。
石田:この生糸商標というのはどれくらいあるんですか。
佐野:私ども最盛期には60以上もの工場がございましたので一つの工場でいくつかの商標を持っておりました。したがって60工場の数倍はあったかと思います。
朝岡:現在も使われてるんですか?この商標は。
佐野:はい。社章にも使われておりまして。
朝岡:(資料を見て)これですね。
佐野:社章の場合は周りが生糸の枷糸と言って縒った糸をですね、これで丸二十を囲んでおりますけど、そういったいくつかの“縦の糸と横の糸を結ぶ”という片倉の精神にも基づいているわけですね。
朝岡:縦の糸と横の糸を結ぶ。なるほどね。これすごいデザインですね。貴重なものをありがとうございます。
石田:優れたデザイン…どなたが考えたんですか。
朝岡:片倉工業デザイン部ってのがあるんじゃないですか。
佐野:当時は工場ごとにこういったデザインを起こしてましたので、工場長の威信をかけてやっていたんだと思うんですよね。工場長ごとの。
朝岡:なるほど。文化も持ってますね。
NEXT100 ~時代を超える術~
NEXT100、時代を超える術。革新を続け、100年先にも継承すべき、核となるモノ・・・。
石田:最後に次の100年に向けて変えるべきもの変えないもの、会社にとってコアになる部分を教えていただけますか。
佐野:創業以来の「信義誠実・親和協力」、この二つの社風でございます。そして、多角経営の基礎になった祖業である「シルク」への思いです。
朝岡:100年越えている長寿企業ですからね。200年というのもそう遠くない将来な気がしますけど、佐野さんその100年後の後継者には、これはぜひ伝えておきたいということがあれば伺いたいんですけれども。
佐野:100年後となりますと創業250年を視野に入れる時代になります。創業以来の「信義誠実・親和協力」、この二つの言葉をですね、この社風は引き継がれてその後も持続的な成長が続くことを伝えるような形にしたいですね。
朝岡:長寿企業というのは100年を越えると次は200年、もっと先ということになってくるんですけど、佐野さんが個人的にお考えな長寿企業に共通する必要なエッセンスというか大事なことっていうのはなんだと思いますか。
佐野:風通しの良い職場だと思っております。もともとは先代社長から引き継いだランチミーティングですけどね、これは私が社長の間はぜひ引き継いで継続してやっていきたいと思っております。
現在は週に一度課長職を集めて、業務後にミーティングをしています。ほんのちょっとお酒入れながらなんですけど、うまくいっている課長、なかなか自分が思っているより先に行けない課長とありますね。同じ部の中ではなくて、仕事が離れた管理部門だったり、現場の部門であったりそういう人たちを織り交ぜてミーティングしてますと、新しくもらった知恵がわいてきますよね。
そういった知恵が活かせるように、私が間に入ってしゃべりすぎないようにしています(笑)。それを続けていきたいと思ってますね。社員一人一人が何を考えてどういう行動をしようとして行動しているのかってことが、私からまた冒頭の人間が感じ取れるような会社にしたいと思っておりますね。
朝岡:現在も使われてるんですか?この商標は。
佐野:はい。社章にも使われておりまして。
朝岡:(資料を見て)これですね。
佐野:社章の場合は周りが生糸の枷糸と言って縒った糸をですね、これで丸二十を囲んでおりますけど、そういったいくつかの“縦の糸と横の糸を結ぶ”という片倉の精神にも基づいているわけですね。
朝岡:縦の糸と横の糸を結ぶ。なるほどね。これすごいデザインですね。貴重なものをありがとうございます。
石田:優れたデザイン…どなたが考えたんですか。
朝岡:片倉工業デザイン部ってのがあるんじゃないですか。
佐野:当時は工場ごとにこういったデザインを起こしてましたので、工場長の威信をかけてやっていたんだと思うんですよね。工場長ごとの。
朝岡:なるほど。文化も持ってますね。
片倉工業、佐野 公哉
「信義誠実・親和協力」
創業から代々受け継がれているこの想いと共に、時代やお客様の変化に合わせて、事業を行っていけるように、「新たな知恵」が生まれる環境を作っていってほしい。
この想いは百年先の経営者達にも受け継がれていくだろう。