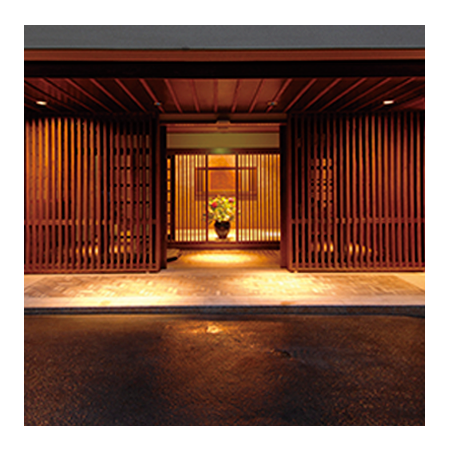
- 2020.10.02
合資会社 一條旅舘〜トップとは、 その道のプロフェッショナル
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは、時音の宿・湯主一條(ときねのやど・ゆぬしいちじょう)20代目代表 一條 一平(いちじょう いっぺい)創業は1560年。
初代一條長吉(ちょうきち)が宮城県白石の「鎌先温泉」に湯小屋を開いたことからはじまる。「鎌先温泉」は「奥羽(おうう)薬湯(くすりゆ)」として、古くから人々に親しまれ伊達政宗も訪れたといわれた。
1891年に旅館業を興し、1928年合資会社一條旅舘を設立。
湯主一條では当主が「一條一平」という名を受け継いでいる。現在は20代目まで続いている宮城県内でも最大級の木造建造物である本館は
鎌先温泉のシンボルともいえる存在であり、2016年には国の登録有形文化財に指定された東北の旅籠文化(はたごぶんか)を、体験できる旅館として多くの人を『幸せな時』を提供し続けている。
今回は、そんな「湯主一條」の20代目代表、一條 一平の言葉から時音の宿・湯主一條の持つ長寿企業の知恵、物語に迫る!
一條:私共の」事業内容は宿泊施設、旅館の運営・経営を行っております。458年目というかたちになりますね。宮城県の中では私共のところよりも古いところが2つ、二施設あるというかたちですが、東北の中ではたぶん古いほうに入ってくるという形になりますね。
歴史という部分もあるんでしょうけれども、私共の一番の強みと言うのが木造の本館、大正から昭和初期にかけて建てられた一部木造の4階建てで建てられているところ、これが現在「国の登録有形文化財」という形になっているんですが、これが何よりも今も残っていてそこを昔は湯治場だったところを現在は個室料亭、全部個室になってますので。その建物が残っていて、今も活用しているというところが何よりも強みだと思っています。
日本人、もちろん海外の方もインバウンドで来る海外のお客様両方とも、私共坂を登ってきて旅館があるんですけれども、その坂を上りきったところの登り口(左手)に本館が見えるわけですね。皆さん必ず初めて見た方は一様に「おー!」という声を必ずあげられる。
で、チェックインをされて、部屋に行ってから荷物を置いてもう一回外に行って。(木造の本館は)時間帯で表情も違ってきますからその写真をバンバン撮影する。特に海外の方なんてほぼ帰ってこなくなるくらいですね。写真を皆さん撮っておられますね。
~一流に触れることが最高の育成術~
私共は、私が元々ホテルマンだったということ。もちろん私共の女将もホテルつながりですのでそういった意味では“ホテルのようなスマートな接客”それプラス東北の温泉旅館ですからそれは場面場面で“旅館の親しみやすさ”だとか“優しさ”って言うのもお出ししますけれども、スマートな部分と言うのも大切にしていますね。
数年前から始めていることなんですけれども、「まずは一流を見ようじゃないか」と言うことになります。「じゃあ一流ってなんなのか?」というのは、なかなか東北のほうにいると極める部分は難しいんですね。
ですので、東京に来てみて、そして最初のころやったのがジョエル・ロブションでフレンチレストランですけれどもそこで皆さんと同じホールの中で自分たちだけのスペースを作ってもらって、ワインのオーダーから。私は一切口出しはしません、全部スタッフにやってもらって一流ってものを体験していただく。
もしくはパレスホテル東京の時にも総支配人がおいでいただいて、そしてコンシェルジュに話をしてもらって「ホテルというものは?」もしくは「サービスというものは?」っていうものをホテルマンから話を聞いて。そしてソムリエからレストランでのマナーであるとか、そういったものを踏まえてから料理がスタートする。
やはり東京は一流のものがいっぱいありますので、そういったものなかなか地方では見れないものを体験させてあげることによってわかってもらう。私や女将が一生懸命伝えたとしても、「いいものを見てらっしゃいと」言っても、わからないんですよ。基準がわからない。
であれば、会社側が研修としてやってあげることによって体感をする。そうすれば、「どういうことを求めているんだろう」そうすると一歩先のお客さまが何を考えているんだろうと言うことが、もしかしたらわかるかもしれない。体験に勝るものはないと思っておりますのでやろうと思っておりますし、今年も実は東京でやろうという形に今計画しております。
本来であれば旅館で本当に丁寧に穏やかに流暢に接客をしている人間が、言葉が出てこなくなったりですね、どういう風にやったらいいのかわからずに。そしてワインのオーダーとかもやらせるんですが、ワインのオーダーしているだけなのに汗を掻いているんですね。ガチャガチャに緊張してしまって。これぞ本当の一流というもの、雰囲気にのまれている。大いに結構じゃないですか。
そういうのをやると、それが自信につながって反対にお客様が緊張しないようにやってあげる、逆の接客もできますよね。いい体験だと思っています。
~日本と海外 接客文化の違い~。
もともとサービス、コンシェルジュということもそうですけれども、私もホテルに勤めているときにコンシェルジュを経験しておりますけれども、誇りをもって皆さん仕事をしていますね。ホテルにリスペクトというか誇りを持っているということももちろんですが、自分がホテルマンであることに誇りを持っている。ですから皆さんの立ち振る舞いがまるっきり違うんですね。
「そこの名前をしょっている自分はホテルマンである。よって背筋をぴんと伸ばし、そして身繕いも。そうした一つ一つを一挙手一投足まで海外のホテルマンと言うのは見ただけでホテルマンだとわかる人がいっぱいいます。
じゃあそれを旅館に当てはめるとどうかというと、若干違う部分がある。まだまだ出遅れている部分がある。しかし海外の人たちと言うのは、日本の旅館であるとか、女将さんであるとかそういうものをものすごく勉強していらっしゃる。でも我々旅館業界はどうなのかと言ったらまだまだ。せっかくサービスという意味では、お客様から“おもてなし”という言葉が飛び交っていますけど、そういうものは日本が先進のはずなのに残念ながらまだ日本はまだまだ遅れているなあと。旅館という意味では遅れているなあという風には感じます。
“一人前”と言うのは、私も含めてまだまだ一人前になっているサービスマンは私を含めてよっぽど出ない限りいると思いません。やはりそこの中で一歩一歩進んでいってるな、進歩しているなっていうのは、「基本を絶対に曲げない人」ですね。
我々で言うと”作法”というのがあります。戸を開け閉めの作法、それからもちろんお辞儀の作法やり方があります。そのやり方をいついかなる時も忙しくても、もちろん暇な時でも絶対に変えない基本を曲げない人、これが本当の一流といいますか、一人前になるための土台ができている人間だと私は思っています。自分も含めてね。
接客を相対してやる人間という意味ではお客さまは色んな感情をお持ちになっていますよね。忙しいかもしれない、夫婦喧嘩をしてイライラしているかもしれない。一人旅をしているのかも、仕事で疲れているかも知れない。そういった人たちに我々が接する時に、その感情に流されてしまったら元も子もない。反対にそういう人たちが何か私共の所にきている。うちのスタッフに「なんてここはしっかり一つ一つに事をやっているんだろう、そんな事で気持ちが「フーっ」となったり、「怒っていることが馬鹿臭いよね」ってなるわけですね。
なので基本はとっても大事だなっと思います。
決断 ~ターニングポイント~
続いてのテーマは「決断 ターニングポイント」
会社の発展と共に訪れた過去の苦難、それらを乗り越えるべく先代達が下した決断に迫る。
一條:私がまだ経営者になりたてのときですね、2003年に世代交代と言う形に成るわけですけれども、2006年の年末、もう12月の年末の迫った12月の26,27の日にですね、3日間降り続いた雨、冬だったらば雪だったはずなのですが本当に大雨が三日三晩ずーっと大雨が降り続けました。
その時に、私共は温泉街の一番上、坂の上の奥まったところにあるわけですが、一本の沢が流れています。その沢が大反乱を起こして土石流が発生すると。朝起きてみたら、目の前が、目の前の道路、そして坂のところが濁流になっていてロビーにはもちろん床上浸水。坂の途中の所にたっている本館のところにも土砂が入り込むというのがありました。
27,28(日)という年末あたりはもう会社(補修業者等)も終わっているはずです。でも復旧させなくてはいけない。
まずは止まっているお客さまを無事チェックアウトして頂く事を考え、そしてその日に泊まるお客さまに関しては、もうキャンセルをお願いし、もしくは予定の変更をお願いし、っていうこともやり。それプラス現場復旧もしなくてはいけない。土砂も書き出さないといけない、本当にそんな事もありましたですね。
あの時は呆然としましたし、漠然としましたが、ただし、それまでのお付き合いもあったんでしょう。「新しい経営者をなんとかして助けてやろう」っていう消防団であるとか、それからそれまでお付き合いをしてきたクリーニング屋さん。そこは清掃業務もやってますから消毒をやってくれました。
それから浄化槽の中には砂が溜まってしまい、使いものにならなくなった。それをなんとかしないと、書き出さないといけない。それもわざわざ山形から車を運んできてくれて、そして土砂をかき出してくれた。そして浄化槽の中にはモーターもはいっています。そのモーターもいかれてしまいました。そのモーターもなんとか手配してくれて。
とにかくなんとか2日間は営業不能となりましたけれども、年末年始営業ができるというところまでこぎつけた。そういう“苦い経験と言うよりも乗り越えてきた”っていう1個1個の一つではありますけれど、そういうことが私共を強くしてくれたのかなと思います。成長させてくれたのかもしれません。
~震災時に下した大きな決断~
3月11日の東日本大震災、そこから我々共は42日間の休業をするという選択を致しました。世の中は、やはり同じ県内ですので、1泊3食で7千円で工事の人たち、復旧作業をしてくれる人たちを受け入れましょう、ということで他の旅館はもう工事業者の方でいっぱいになってます。でも私共は、ガラガラ。休業ですから。一切そういう(復旧作業)のを受け入れていない。
色んな事も言われました。色んな陰口も叩かれました。「皆で助け合わなきゃいけない時にお前はひどい」ということも、陰口を叩かれました。
しかし、なぜ私共が休業という選択をとったのかといいますと、湯主一條というのは市場、お客様から見てどういうものを求めているところなのか?やはり、心地よい空間できれいなところで、気の利いたスタッフがおいしい食事を、そういうものを楽しみに来てくださいます。
それを1泊3食7千円で入れることによってそれは全部崩壊してしまう。だとした時に私共は、「休業」。あえて、泊めないんじゃないんです。あえて「休む」という選択をし、そして色んな所に方々に連絡をし、その時にはJR東日本というのがキーワードです。
新幹線が動き出したらまた、世の中変わりだす。高速道路が動いているのはわかりました。やっぱり輸送能力のある、お客さま、旅行する人たちを乗せる、東北新幹線、これがいつ動くのか、ということの情報をほうぼうから集め。そのために復旧工事をしたわけですから。
であれば復旧工事が終われば、また観光に来てくれる人がいる。お金を使ってくれる人が首都圏からわんさか来るはずだという見立て、仮説を立てて、じゃあ東北新幹線が開業するまでの間に、設備投資をし、今までできなかった駐車場の整備屋根の整備、もちろん館内の大掃除、そういったものをやりながらお客様を迎える準備、もちろん、休業していますから私たちは働いている訳ではないので。接客レベルもこのままでは落ちます。
ですので接客の作法をもう一度この機会にやり直したり。それからどういう順番で接客をするんだっけ、お客さまをお迎えするんだっけ?ということもやりながら。料理の方も、1ヶ月以上もやってなかったら腕も鈍ります。料理長が私たち相手に真剣に勝負の料理を作ってくれるようになって。一つ一つ積み上げていって。
そして、42日目を迎えてちょうどゴールデンウィークのちょうど4月の終わりくらいからスタートしますけどその時に、稼働率96%と。一部屋だけ埋まらなかったんですが、それでスタートが切ることができるという奇跡が起きました。
それは震災が起きて色んな会社がですね、人を解雇するだとかもしくは営業停止する、もしくは廃業するということになってしまっているのを見て、やはりそれだったらば無理だと言う所もあり、私共が金融機関にお願いをし、それなりの資金調達をし、そういった意味では余力を持った上で全員解雇しない、一人も解雇しないっていう方針を打ち出したおかげでスタッフは安心できますね。
ここで今はやっていないけど、そのまま働くことが出来る。本当に世の中がまたそういう状況になったらまたここで働けるっていう安心感が。じゃあ次のステップ、ということを考えられる余裕ができたんだと思います。
~一條一平のターニングポイント~
私の最大のターニングポイントというのは“世代交代”。それは父の死、急死という言い方のほうが正しいかと思います。
それは2003年の出来事であるわけですが、本来一緒に仕事をしたかった父が自殺という選択を取ります。実際に私が本日只今よりお前が経営者というように成るので、通帳見たり、それから支払状況を見たりするたびに、まるっきりお金がない。父は自分にかけている生命保険これで会社を立て直してほしいという遺書を私宛に書いております。それも今持ってますけど、それが私の一番のターニングポイントですね。
なんとかしなきゃということ、それから眼の前に置かれている宿題がいっぱいあるわけですね。それを一つ一つこなさなきゃいけないということで日々追われていたので、泣いている暇がなかったっていうのが振り返るとそう思います。
2003年にそういった形で世代交代が急に始まりまして、自分が社長となる。その時に自動的に妻である者が女将に成る。父はもういませんから、母も現場を去って違うところに行く。要は、本当に私と妻しかいない状態になったわけですね。
その時に実は鎌先温泉に返ってきた1999年からその父が亡くなるまでの間、妻が子育てをしながら、自分だったらこういうふうにしたら面白いのに、ここにあったらお客さん喜んでくれるのになって言うことを2冊のノートにまとめてくれていたんですね。その中のことを一つ一つ実行に移していったということになります。
その一つが2004年に湯治場だった木造本館のところの一部を個室料亭にする。もちろん一部はまだ湯治っていう湯治場っていうのは残していたんですが、それをまず最初にやった所大変お客さまからの評判が良かったというところはあります。
2008年の全館総リニューアルっていうのは基本的にはもう女将がああしたい、こうしたいということを、もっともっと増やしていったということになります。
そもそも私は外交というか、外で金融機関であるとかもちろんいろんな商売やっている人たちと外向きに色んなことをやっていました。(旅館の)中を収めているのは女将なんですよね。スタッフのことだとか、お客さまのことだとか常日頃現場を見ているわけですよね。
現場を見ている人間が、あれやりたいこれやりたい、こうやったらお客さまが喜ぶ、こうやったらスタッフは動きやすくなるって言っているのを、もちろん私はダメというときもあります。そうすると、大喧嘩に成るんです。当たり前です。「あなたは現場をわかっていない」ということで。そしたら引き下がるしか無いですよね。
そして女将がやりたいってことが図面に上がってくる、絵になってくる、パーツになってくる。そうすると、「あーやっぱりやってよかったんだな」と結局なりますので、これはやっぱり役割分担です。私は余分なことに口を突っ込まない。もちろん予算がありますので、その予算の中で、ここは予算オーバーだからなにか知恵を出さないとという言い方はしますけど、やることに対して「NO!」ということを言ったら行けないんだなということを途中から学んで、もう好きなようにといいますかできるだけ具現化出来るように皆で努力をした。
~代表就任までの経緯~
私がホテル学校に行った時にお世話になったホテルにまずは就職することになります。そして程なくして、妻と結婚を考えることになりまして、その報告をしに、実家に戻ります。
ところが、母は大反対です。もちろん父は後押しはしてくれるものの、父にそんな権限といいますか、パワーはないんですね。
それから執拗な嫌がらせとか、色んなことをされまして、「もう私は旅館の後は取らない」「もう二度と返ってこない」ということで東京に戻ってきまして、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイに入社をすることになります。
そして配属されたフロントで少しずつ実績を積み、そして念願であるコンシェルジュという籍に置くことができ、今現在も日本コンシェルジュ協会のメンバーであるんですけれども。
そんなこんなしているときにですね、東京でホテルマンとして「さあ!これからだがんばっていくぞ」という矢先、本当に人生って面白いもんですね。犬猿の仲であった母親と東京の地でですよ、バッタリ会うことになるんです。ありえないと思いましたがこれもやはりご先祖様に呼ばれてしまったのかと思いますが、今となってはね。
そしてそこで母に言われたのは「助けてほしい」という一言でした。どうしてかと言うと、これから露天風呂のビルを新しく建てるんだが、金融機関が破綻してしまった。そして、それに付随して融資がまあすぐでなかったですから、引受が決まるまではでない。そしたら、工事を請け負っていた工務店まで倒産してしまった。「にっちもさっちもいかない、助けてほしい」その言葉にやはり私も心を動かされ、戻ってしまいました。
「戻ってしまいました」という言い方になるのは、戻りますが、戻って私が連帯保証人に判子をおします。もちろん工事は進みます。
ところが、もともと結婚に反対だった母は、私が妻と一緒に戻ることによって「おもしろくない」と、判子を押してくれればそれでよかったんですよね。
で、結局“嫁姑問題”が勃発します。
1999年に戻り、1年後の2000年にまた東京にでてくる形になります。そして、1年間なんとか東京で生活をしていたんですが、色々ありまして、2001年にまた旅館に戻ると言うことになります。
そして間もなく、2001年に戻ってそれから2年後の2003年5月に父が亡くなる。自殺をするということになりまして、そこで世代交代。そして現在に至るということになります。
母の・・・私の母のあのパワーに勝てる人間(妻)を無意識のうちに選んでいたのかなぁという風に今となっては思っております(笑)普通の人でしたら多分音を上げるでしょうね。
でも、やはり妻は女将として上に立てる人間ですので、そこのあたりは根性の入り方っていったらおかしいかもしれませんけどね。信頼を置くべきパートナーであると私は思っておりますけどね。
~主になる者の宿命~
旅館の中で遊んでますので、仲居さんであるとかとにかく旅館のスタッフ、お客様、それから鎌先温泉街の中の人達、皆が私のことを名前で呼ばないんですよ。「若旦那さん」っていうんですね。
「若旦那」ってうちの父を見ると「旦那様」って言うわけですね。で、祖父を見ると「大旦那さん」って言われるわけですね。ってことは若旦那イコール次の経営者ってことに子どもながらに自動的に思います。もちろん父からは何回か、「お前がここを引っ張ていくんだ」この「引っ張っていく」っていう言い方じゃないですか。もう無意識のうちに周りはそうやって「あなたは次の後継者です。私たちは認めています」というのを周りが仕組んでくる。
これは今思えばすごい哲学だなと思いますね。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
続いてのテーマは、「言魂、心に刻む、言葉と想い」
家族や先代、恩師から受け取った言葉
そこに隠された想いとは?
一條:一つの言葉は、「想像=創造」という言葉です。
最初の「想像」っていうのは考えるって方ですね。イメージをする方の想像です。
で、創り出す方天地創造の創造ですけど、創り出すのとイコールであると私は思っています。この言葉が同じ発音なんで好きなんですけれども、要は自分が思い描いたことはイコール行動することによって形造ることが出来る。今着ているものもそうです。なにもなかった。それを思い描いて、紙に書きだしてそして必要な行動を取ることによって創り出すことが出来る。要は、地域でやったとしても会社でやったとしても、どういうことを想像しながら創っていくのか。未来に対してもどういう未来を想像して、自分はどう行動してやっていくのか。未来についてはこれからですのでわかりませんが、自分が今一個一個想像してやっていることが、未来につながってくれれば良いなあと、言うのが一つです。
そしてもう一つ気をつけていることが、「誰と」ということですね。これは最も大切にしていることです。
ちゃんとした人と言ったら変ですけれども、やはりそれなりに実績を積まれてきた誠実な方と私は仕事がしたいというふうに思っております。やはりダメになる人はダメになる人のチームになっちゃうんですね。伸びてくる人たちは伸びてくるものを持っています。私はそういう人たちと仕事をしながら、自分も成長させてもらいながら、そして仲間として、そして仲間を成長することで自分の持っている自分たちのチームも、もっともっと成長していく。
「誰」と仕事をしていくのか、「誰」と組むのか、これはとっても大切なテーマだと言う風に思っております。
貢献 ~地域、業界との絆~
「地域や業界との絆」
一條一平が行っている地域や業界での取り組み。
そこに込められた想いとは?
一條:今現在子どもたちが学生ということもありますので、PTA会長をやったりもしくは、2年前に誕生しました新しい市長の只今後援会長を務めさせていただいております。
そしてやはり鎌先温泉、宿泊・・・自分の所の旅館という意味では、地域に対しての愛情というものを考えながら行動をしております。
例えばですけれども、一個一個の旅館が頑張ったところで、たかが知れています。じゃあ鎌先温泉としてどうするの?まだ具体的に進行しているものはありませんけれども、こういう事ができたならば、鎌先っていうのが発信できるよね、っていう図はもうできています。それをどの順番でどう優先順位を決めて、どういうふうな順番でやっていったらいいのか、それを金融機関それから政治的なもの色んなものがあります。優先順位を決めて、現在進行系という形で取り組んでいる最中という形になります。
そして、現在は私共の蔵の中に入っていた一部の古文書、これを今東北大学の方で解析をしてもらっています。中にどういう事が書いてあるのか、目録にしていただいている最中なんですけれども。
どうしてそんな事をしているのかというと、もともと鎌先というところがどういう地域だったのか、どういう事で発展をしてきたのかということが底につぶさに書いてある。
要は私の一つのテーマである、ピ「鎌先を昔に戻す」というのが私の中でも一つのテーマであるんですね。
昔は一体となって、鎌先が一つとなってお客様を受け入れ、そしてそこでは政も行われ、っていった写真もあります。昔のようにそういうふうになれたら良いなということで、そういう解析をしながら、どんな場所だったのか、そういうところも踏まえながら、鎌先の将来、地域の将来というものを考えていきたいと思っています。
NEXT100 ~時代を超える術~
NEXT100、時代を超える術。
100年先にも変わらない「湯主一條」にとって核。
そして、未来を見据え、変える必要のあるもの。
20代目 湯主一平が語る。
一條:これはまさしく私共のピ木造本館、只今現在国の登録有形文化財に指定をされているこの木造を遺すこと。そのためには維持・管理、丁寧に使い続けることこれが何よりだと私は思っております。
建物だけではなくて今私共に評価をしていただいている接客サービス、料理の質、そういった“人の関わるもの”そういったものをずっと維持していくこと。そしてましてや時代に合わせたサービスマン、サービススタッフを育てていくことを課せられている、宿題だと思っております。
~次代を担う後継者へ~
世は無常であるというように思っております。無常というのは常に同じではないという意味の無常です。世の中ってグラデーションで変わっていると思うんですね、私は。携帯電話もだんだんだんだん変わってきました。携帯電話から今はスマートフォンに変わりました。
そして、私たちの着ているものも、少しずつ変わってきました。世の中の建物さえも変わってきました。すこーしずつすこーしずつグラデーションで変わってきている。
なので、世の中の変わり目、「あ、なんか違くなってきた」という情報であるとか、肌で感じるものに敏感になってもらいたいという風に思っています。
そしてもう一つは「陽極まれば陰となり、陰極まれば陽となる」という言葉があります。要は「良いことばっかりはありませんよ」ということです。落ちることもあります。もちろん陰、悪いことばかりでもありません。必ず上がってきます。要はこれも無常と同じですよね。
常に一緒じゃない。常に動いている。だとしたら良いときほど悪くならないようにあぐらをかくことなく良いときほど真剣にやらなきゃいけないし、注意力を持たなくてはいけない。
じゃあ悪い時にジタバタせずにデーンと構えて少し何もしないくらいの余裕をもった、そういった経営者、もしくは後継者そういったものをなってもらいたいなあと言う風に思っております。
一條家は男子が跡を取るものだと家訓の中でずーっと脈々と繋がれてきていることであります。私もよって長男である、男一人しかおりませんでしたので、私が後を継ぎました。
これからの時代どうなるかわかりません。息子、私もおります。息子も経営者になるという意識はあるようです。私は無理強いをして旅館を継げと言うようなことはしません。やりたくなればやればいい。やりたくなかったら別の仕事を探すのも良い。私はそう思っています。
じゃあその時に、湯主一條をどうするのかということがありますが、今現在は私は答えを見出せておりません。適切な時に適切な場所でその答えが見つかるものだと思っておりますので、そのあたりはこれからもしっかりと見ながら、そして息子を将来世界に通用するような人間になるように育てていきたいなという風に思っております。
~長寿経営を行う上で一番大切なもの~
やっぱり地域に対しての愛情なんでしょうね。自分が生まれ育った所に私は戻ってきました。そこに愛情がなかったら戻らないですし、そこに愛情がなかったら会社を続けていこうとも思わない。会社に対しての愛情は誰しもがあると思いますが、じゃあそこで一人でやっているわけではないので、それが自分の愛せる地域なのかどうか、ここは大きなポイントだと私は思います。たとえそれが偏僻なところであっても大変便利なところであったとしてもそこに愛情があれば、何かしらの打開策というのは絶対に見つかるはずなので。私はそう思います。
私はこういう接客サービス業という形になりますので、私が思うのは社長自らがトップ自らがプロフェッショナルでない限りそこを守り切ることはできないと思っております。そうでなければなぜそこで生まれ育って社長になろうと思ったのか、戻ってきてやろうと思ったのか、理由付けに私はならないと思います。
よってこれは接客サービス業ということになるのかもしれませんが、その道のプロフェッショナルになるということが、何よりの長く続けられる企業、会社、地域というものにつながっていくんじゃないかなあと私は思います。
時音の宿・湯主一條20代目一條一平が、次代へ届ける長寿企業の知恵…。
その道のプロフェッショナルであること
トップ自らがその道のプロフェッショナルでない限り会社・社員・地域を守ることはできない
この想いは100年先の後継者へ受け継がれていく・・・
ここからは、テーマにそって、「湯主一條」の持つ長寿企業の知恵に迫る。
最初のテーマは、「創業の精神」。
創業者の想いを紐解き、家訓や理念に込められた想いに迫る。
一條:私共今旅館がお泊りになるところが、現代。そしてお食事をする場所が古い個室料亭でという事で、タイムスリップ、タイムトリップ、その”時間“っていうものを一つのテーマにしているんですね。ですので”時音”っていうのは、昔から来た旅人の足音が聞こえるような、そういうずーっと歴史感の感じるようなそういう宿なんであるということをお伝えするために、”時音”という名前を使いました。
なかなか湯守であるとか湯本であるとか、要はお湯を持っているというある種の“湯主”という言い方をなかなか聞かないと思うんですね。昔から私共”湯主”という言い方を聞かないと思うんですね。昔から私共湯主という言い方をしている。これはまあ先代から聞いていることですけど言い伝えられていることは、もちろん温泉の主であるということ。
もともと私の方は一軒しかございませんでした。今は5件ありますけれど、他の旅館は存在しませんでした。そうすると、すべてのお客さまが私共のお風呂に入るということになります。
そして時代が変わりまして、土地を与え建物建てさせて私共を入れて4件の旅館がでてくる時がありました。この4件の旅館があったしても、温泉の源泉を持っているのが私共の旅館です。渡り廊下で全部つながっていたんです。要は結局はお湯の元は私共のところにあるということ。
そして(昭和)40年代の後半になりまして、温泉法という法律が変わりまして、それぞれ掘削をさせて、実は分湯しているという時代もあるんですね。
私共一店だけの温泉。それから渡り廊下で各旅館を結んでいた。そして私共のところから分湯をしてあげていた。そして現在は(温泉の源泉を)掘らせてあげていたってことになるんですが、結局そのお湯の元を持っているという、あるじ、主であったと。それから鎌先のほとんど、それから昔の福岡の中でも地主であったこと、ということも含めて「湯主」と。誰が主だ?という事で「一條」であるということを伝えるために湯主とつけたと聞いております。
~一條家の使命~
私共、ちょうど私で20代になるのですが、ずっと代を追っていくとですね、14代目、15代目、16代目、17代目この4代にわたって村長さんをしていた実績があります。
その中でやはり村人のために保証人になってあげて、村人が生活できるようにやってたと、そういう風に言い伝えられておりますけれども。
で、17代目の時に大繁栄はするんですが、繁栄はした変わりにやはり失うものも大きかったようです。村人の保証人になったりとかして、自分の所の財産を取り崩す、ということもあり、それ以降政治に関わるな、ということが父からは言われております。
先代の父からは政治に関わるなと言っている割には鎌先をずっと背負って立つこと、鎌先の将来を考えることは一條家にしかできないことであると。私にしてみればその時はよくわからなかったのですが、その言葉を言われて、そうかと。湯主一條という会社を存続させる事も大切なんですが、鎌先温泉という温泉地を今後も次の世代に、また次の世代に残していかなければいけない。”地域を残していく“っていう仕事も私にかせられているんだなということもその時思いましたね。
ただ残るんじゃなくて、やっぱりそこに人が足繁く行ってみたい。あそこに行こうよって“選ばれる場所”にならないといけないわけですよね。「そのためには」ということを今は日々考えながらやっているという感じです。
スタッフに対してということですと、毎日社訓それから経営理念の唱和って言うことをするわけですね。仕事始まる前にその部署ごとに全体でやる場合もございますし部署ごとによることもございます。
そして、それだけだと同じことの繰り返しになりますので、その時その時もちろん理念であるとか、社訓の中のテーマに沿ったものもありますし。その時に必要なスタッフに対しての、今起きている問題であるとか、もしくはこれから目指す方向である、そういったものを私がA4用紙の一枚にまとめまして、毎月の給料明細の中に入れて、私からのメッセージという形でお伝えをしています。
~代表就任後に行った改革~
私共の制服なんですが真夏はちょっと違うとしてもですね、私共の制服は男性も女性も黒服。俗に言うスリーピースという形になります。
よく旅館といいますと着物を着たり作務衣を着たりというのが一般的と言われております。私共もよくお客様に言われるんですね。駐車場から旅館までご案内致しますと、玄関にたっているスタッフが男性であれ女性であれ黒塗りのパンツスーツをスリーピースを着ているスタッフがズラッと並んでいる。そうすると、「なんだか緊張するな、ここ旅館なのに」という風に言われますが、なぜ旅館だったら着物じゃなきゃいけないんでしょうか。じゃあなんで旅館だったら作務衣じゃなきゃいけないんでしょうか。それは、先入観ですよね。
それに私共は、先程申し上げた国の登録有形文化財。お客さまのいる客室のスペース、料亭のスペースは確かに冬は暖かく、夏は涼しいです。空調もちゃんと入ります。周りが廊下になっているんですが、周りの廊下は外気温と同じです。冬は寒いです。ですから着込めるように、色んなものを着込んで暖かくして風邪を引かないように暖かく過ごせるように。
ましてや私共は階段ばっかりです。着物を着ていたら裾を気にして歩くことすらかなわない。機能性、そしてもちろん動きやすさ、そして暖かさ。そういうものを兼ね備えるためにそうした。私共はもちろんホテルの出身だってこともあり、ホテルの要素も取り入れたいという事もありましたから色んな要素を加味して制服を変えたんですね。
実はそれが好評だったりもします。ちょっとこう・・・緊張する。でもその緊張も心地良というお客さまもお出でいただくのも確かなんですね。
私共のところでリピーターになっていただけるお客さまは、初めてきても「ここ気持ちいいね」と行ってくれるのはそんな要素です。きちっとした振る舞い、非常に背筋を伸ばして。だけれども、ある人は方言で、方言が抜けなくて方言で喋っている人もいたりする。地方から来ていて若干イントネーションが違ってなかなかそれが抜けない。でも誠実さがちゃんと伝わっていて、そしてお客さまに届いていればそれは良いことだなと思いますので、まずは制服を大きく変えているというところがあります。
お金をかけて、時間をかけて、ましてや車ないし新幹線などの公共交通機関を使って移動という行動までしておいでいただくのに、そこにダラダラの風景が待っていたらお金払いたいと思いますかね?私だったら思わない。この旅行は本当に無駄だったと思うと思います。
でも、心地いい緊張、ちょっと緊張するかもしれないけどそれぐらいの気持ちが伝わるんですね。お客さまとして行った時に伝わります。我々がだらーっと歩いてお迎えしたら。「(だらっと)いらっしゃいませ~」というのと「(シャキッと)いらっしゃいませ!」というのではまるっきり違う。そこにお客さまは価値を見出して、「またくるよ」と言ってお帰りになる。