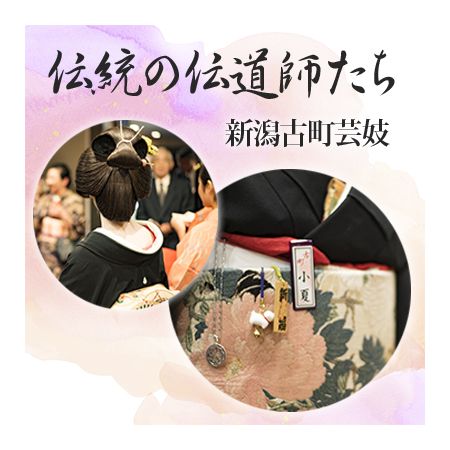
- 2020.10.03
伝統の伝道師たち 新潟古町芸妓
古町花街で多くの人々をもてなしてきた新潟古町芸妓。
古町芸妓は、若手が「振袖さん」、ベテランが「留袖さん」と呼ばれる。
振袖さんの育成と地域芸能の伝承、文化の振興を目的に設立された柳都振興株式会社。設立から30年、風に揺れる柳のようなしなやかさで時代の変化に適応してきた。
柳都振興はいかにして誕生し、古町芸妓の伝統を次代に伝えていくのか。

シルバーホテル 取締役相談役
中野 進(Susumu Nakano)

藤田金屬 代表取締役社長
今井 幹文(Motofumi Imai)

行形亭 当主
行形 和滋(Kazushige Ikinari)

高橋 すみ(Sumi Takahashi)

たまき(Tamaki)

あおい(Aoi)
柳の都 新潟

北前船の「日本海側最大の寄港地」といわれた新潟。北前船は江戸時代から明治にかけて、物を売買しながら北海道~日本海各地、下関を回って大阪へ運航した船だ。
寄港地として多くの人と物が集まった新潟の古町エリアは、港湾都市として整備され、かつては堀がめぐらされていた。通りには蔵がずらりと並び、植栽された柳が優美に風に揺れる。そこから柳の都、「柳都(りゅうと)」と呼ばれた。
今井:「見渡す限りに柳が植えられ、どこからでも柳が見えたそうです。」
北前船の寄港地としてにぎわう新潟には花街が生まれ、訪れる人々をもてなした。古町芸妓は、200年の歴史があるといわれ、質の高い唄や踊り、鳴物などの芸でお客を楽しませてきた。
新潟市には日本舞踊の流派・市山流がある。市山流は新潟市無形文化財の第一号。地方の宗家で120年以上の歴史を刻んできた流派は全国でも唯一だという。芸術性が高く評価されており、古町芸妓の指導や舞踊会の企画構成、新潟の花柳界発展に尽力してきた。
踊りに加えて方言がまじった「花柳界ことば」も、新潟情緒を感じてもらうためのもてなしの一つだ。男性客を「あにさま」、女性客を「あねさま」と呼ぶ。「~してください」は「~しなれて」。例えば「お飲みになってください」は「飲みなれて」と言う。
また、手遊びでもお座敷を盛り上げる。「樽拳(たるけん)」は、樽を叩きながらじゃんけんをし、負けた人が1回転してまたじゃんけん。連続してじゃんけんに勝つとゲームに勝利するというもの。手遊びは「軍師拳」「検校さん」など何種類もあり、負けると罰ゲームとしてお酒を飲み干すことも。
花街文化を支えるのは、料亭・待合・置屋のいわゆる「三業」だ。新潟の花街を支えるのは、新潟三業協同組合。料亭などの店と置屋をつなぐ役割を果たし、古町芸妓が活躍する舞台を整える。
舞台の中心となるのは、江戸時代中期創業の行形亭や、江戸時代末期創業の鍋茶屋といった料亭だ。海の物、里の物、山の物…豊富な新潟の食材から生まれたおいしい料理とお酒、お座敷の場を提供する料亭は、新潟の花街とともに発展してきた。歴史ある木造建築、しつらえ、美しい庭園や趣向を凝らした器など目に映るすべてに日本文化の粋が集まる。
最盛期には300人いたといわれる古町芸妓。一日に何度もお座敷に上がり、夜中まで料亭の玄関が下駄で埋め尽くされた。
そして、その三業を支えてきたのが、港町・商都として、また国内屈指の米どころとして繁栄した新潟の豪商・豪農たちだ。彼らが「旦那衆」いわゆるスポンサーとなって、置屋を支え、芸妓を育ててきた。江戸時代から明治、大正、昭和と連綿と続いてきたが、時代の荒波が押し寄せる。戦後の財閥解体、農地改革で豪商・豪農はいなくなった。
中野:「旦那という言葉は、『与える』『施し』といった意味のサンスクリット語『ダーナ』に由来するそうです。置屋に一人か二人若い子を住まわせて、三食出して、お師匠さんのところに習い事に行かせて、着物も仕立てて、学校にもやって…。とにかく半端じゃないお金がかかる。旦那衆が置屋を支えていましたが、そういう人たちがだんだんと減っていったんです。」
旦那が減れば、芸妓も減る。古町芸妓のなり手は半分、また半分と減っていった。ついには振袖さんが一人もおらず、一番若手の芸妓でも30代後半というところまできた。
旦那衆を会社組織に

古町芸妓を守るために音頭を取ったのが、新潟交通社長(当時)の中野進だ。商工会議所の副会頭も務めていた。
中野:「新潟の経済界でも、古町芸妓の燈火が消えそうだ、後継者がいないどうしようと思案していました。でも名案がないままズルズルときてしまって。それでいよいよという時に、旦那がいないんなら、みんなで旦那衆になろうと、会社を設立しました。旦那衆を会社という組織にしたという感じですね。
宝塚歌劇団がヒントになりました。宝塚は阪急電鉄の創業者が発案。宝塚温泉の隆盛を図るために神戸、大阪から電鉄を敷いて、歌劇団を養成した。じゃあ新潟は、新潟交通が中心になってやろうじゃないかと。地元企業80社が出資に賛同してくれました。かつての『柳の都』にちなんで、社名は柳都振興にしました。」
1987年(昭和62年)12月、柳都振興が誕生した。芸妓を社員として雇い、育成し、派遣する。置屋と旦那衆の役割を果たす会社だ。柳都振興の芸妓は「柳都さん」と呼ばれるようになった。
中野:「好条件でないと人が集まらないだろうと考え、当時の高卒の女の子が会社員になってもらう給料の倍は払うことにしました。それから、寮としてアパートの部屋を用意して、もちろん社会保険も完備。成果配分で、1年に一度くらいは賞与も。」
あおい:「それは私の時代も、大きかった。こういうお仕事で、福利厚生がしっかりしているんだってびっくりしました。」
高橋:「会社設立の資金は順調に集まりましたが、かつらやお着物などの初期投資にものすごくお金がかかりましたね。」
行形:「一番お金がかかる、かつらも着物も会社持ち。ほかの芸妓さんからはうらやましがられるみたいですね。好条件で働けて、寮があって、社会保険があって、有給休暇があって。そんな恵まれた環境はないって。」
資金は順調に集まり会社を設立したはいいものの、肝心の芸妓候補を集めるのに苦労し、1期生を10人集めるのに丸1年かかったという。会社員、百貨店の販売員、喫茶店のアルバイト、いろいろなところから人を集めた。着物を着たことがない、正座をしたことがない、白塗りなんてとんでもない…。素人を一から指導する難しさもあった。
高橋:「柳都振興設立当時は、古町芸妓のお姐さん方が75人くらいはいました。何が良かったって、柳都の若い子たちはお姐さん方と同じところでお稽古をしたこと。地元の市山流でもお稽古して。お姐さん方と一緒にお座敷に出て、マナーや芸を学んでいったんです。1年に一度、踊りを披露する場もあって。」
「ふるまち新潟をどり」に魅了され、芸妓の世界へ

あおい:「私も芸妓になる前に『ふるまち新潟をどり』を見ました。たまき姐さんとさなえ姐さんが黒引きを着て踊ってなって。それを見て『はぁーっ!』と。私の隣に、お二人のどちらかのお友達がいらして、その方々がステージを見て『ほら、同級生よ』っておっしゃったんです。
失礼ですけどお隣とステージを見比べて、『同級生ってどういうこと?』ってびっくりしました。美魔女という言葉が出る前でしたけど、そういう感じでした。『何を食べているんだろう』って。かっこいいと思いました。」
たまき:「いや、ステージは遠いしね。塗ってるし。ライトを浴びるといろいろ消えるから。その同級生、私の友達かもしれない。いまだに結構見に来てくれるから。」
今井:「初めの頃は踊れるものがかなり限られてくる。それでもお姐さん方の指導できちんと形になっていった。そうすると見ているお客さんの要求も高くなってくる。それでまたレベルが上がる。」
中野:「やはり市山流の存在が大きい。お師匠さんがものすごく熱心で、親身になって何も分からない若い子たちを一から教えてもらって。踊りだけじゃない。この世界の常識もですよ。」
景気のあおりを食らう花柳界
バブル景気がはじけ、次第に料亭を使った接待がしづらい風潮に。接待が少なくなれば、料亭も閑古鳥が鳴く。そうなれば、お座敷遊びがなくなり、芸妓の出番もなくなる。
中野:「景気がいい時は、お座敷が18時、20時、22時の3回転。私が現役の時は、一次会を料亭で、二次会は同じ料亭の小さい部屋か、少しこじんまりとした店でするんですが、芸妓も一緒に行っていました。」
高橋:「よそからいらした人は、『新潟は畳、畳、それから絨毯なのね』とおっしゃっていました。他のところは料理屋からクラブに行くので、畳から絨毯に移動するんですよね。『新潟は不思議ね』って。とにかく夜が長かったんですよ。」
中野:「夜が短くなると、柳都振興の収支が合わない。だから後援会の仕組みを作ったんです。私が挨拶に回って、みなさん『あんたが来たんならしょうがないね』と言って、協力してくださいました。今、後援会に入っている企業は100社ぐらいです。
けれど、本来はそういう姿じゃなくて、自前で収支を合わせるのが事業だと思う。だから、今から知恵を出して新しい商品を設定しないと。まち全体がそういう雰囲気になれば。」
花柳界の未来を見据えて新たな取り組みを始めた古町芸妓

今井:「人件費を含めた経費と売上がアンマッチ。バブル景気の頃でやっとトントンです。自分たちだけの力で食べていけない事業が、本当に続くのか。お姐さん方が引っ張ってくださった30年前と今は違う。30年前は70数人いた方々が今は10数人という世界。でもお姐さん方の芸がないと、柳都振興だけではやっていけない。芸妓は若ければいいというものではありません。お座敷でいろんな遊びをするにしても、お姐さん方の三味線や踊りがあって成り立つ。
じゃあ柳都はどうしていくかと考えて、もういっぺんきちんとお稽古を付けようとなったんです。3~4年前から新潟市に協力してもらって、東京から長唄のお師匠さんを呼ぶほか、三味線や笛も。大変な量の練習を柳都の芸妓たちにはしてもらっています。」
あおい:「そういう意味では、今の子たちがうらやましい。私が入社した13年前は、踊りの稽古しかなくって。」
今井:「当初は踊れたらいいという感じだった。三味線はお姐さん方にお任せして。三味線を覚えると、お姐さん方の領分を取ってしまうことになるとの考えもあった。でもそうは言っていられなくなりました。踊りも演奏も覚えないと、これから先、続けられないかもしれない。」
あおい:「最初は何も知らないから、『お姐さん方の鳴物かっこいいな』と言ってた。そうするとお姐さん方が『あなたたちもお稽古すればいいのに』って言ってくださって。それで私が2年目の時に鳴物のお稽古が始まった。お姐さん方に憧れていたので、あれもこれもやりたいって思っていました。」
今井:「芸妓たちの努力はなかなか外の世界の人、市民の方には分かってもらえない部分があるので、みなさんに知ってもらおうという活動を始めました。テレビなどのマスコミも盛り立ててくれて。」
高橋:「我々料理屋で、お昼の簡単なお食事を用意して、芸者衆の踊りを見てもらう会を企画したり、芸妓が地元の小学校で課外授業をしたり。芸者衆にとっても、いい勉強になっているみたいですね。」
あおい:「最初に小学校へ行ったのは、私たちの代です。その時に課外授業をした小学生がもう18歳になるんですよね。その子たちが、柳都振興に入ってくれたら嬉しいなと思いますね。柳都振興や三業協同組合、お料理屋さんなどいろんな方たちが考えてくださって、場数を踏ませていただきました。」
今井:「花柳界だけじゃなくて、商工会議所などのみなさんが『こういうことをやってみたら?』と提案してくださったり、後援してくださったり。新潟では花街文化を大事にしよう、芸妓を育てていこうということが連綿と続いてきている。ありがたいことですね。」
行形:「三業協同組合は、待合・料亭・置屋が一緒になった組合で、芸妓さんと、芸妓さんの舞台になる料亭と常に一緒に歩んできました。これからもそうです。」

華やかな世界だからこそ、世間に自粛ムードが漂うと、あおりを食らう。災害が起きると、もちろん影響を受けた。2004年(平成16年)10月、中越地震。2011年(平成23年)3月、東日本大震災。電話が鳴れば、キャンセルの連絡だった。しかし会社組織だからこそ、苦しい時期も乗り越えられた。
あおい:「卒業して、柳都振興のありがたみをすごく感じています。なんて手厚い会社だったんだろうって。独立する時に『柳都から仕事が回って来なくなるだろう?大丈夫か?』と周りから心配されたんですが、今でもよくしていただいています。
一人でやってみたいという気持ちを伝えたのも、柳都が最初でした。それはやはり親も同然なので。置屋だとお母さん、お姐さんと呼び合うでしょ。柳都も一緒なんです。現場の支配人のことはお母さんと呼んでいました。会社って言っても家族みたいなんです。独立のことを相談すると『やってみなさい』って。『でもやり方が大切だから、相談しながらやっていこうね』って背中を押してくれました。」
行形:「柳都振興が長く続いてきたのも、田中さんという初代支配人がみんなから『お母さん』と慕われたから。田中さんがいたからこそ、みんな続けてこられたと聞いています。」
高橋:「田中さんのお母さんが芸者衆で有名な方だった。花柳界のことも詳しいし、お師匠さんとか、お姐さんとか、料理屋の間でクッションみたいな役割をしてくれたんですよね。」
あおい:「好条件だけでは続かなかったと思います。東日本大震災の時もありがたかった。お座敷がなくてもみんなで柳都に集まって、『この間に頑張ってお稽古しようね』って励まし合いながら練習しました。」
渡された次代へのバトン

設立から30年。柳都振興はベテラン芸妓との共存、三業や地元企業、行政など多くの人の支えで古町芸妓を守り育ててきた。
中野:「この30年は何とかやってこられた。でもこの先10年、20年を考えると、今いるお姐さん方は誰もいなくなる。そうすると、新潟の花街、花柳界を支えていくのは柳都振興しかいない。
日本中の花街を見てみると、だいたい芸者衆の最低規模は20人。20人を切ると雪崩現象でダメになってしまう。大きな宴会をやる、発表会をやるとなった時、20人はいないと仕事にならない。今は柳都振興だけで10人なので、20人は確保したい。新潟の場合、ほかの花街よりも大きいから30人はほしい。10代、20代、30代、40代とバランスよく人材を確保できたら。そして、収支が成り立つようなアイデア、戦略を立てていく。
新潟は昔から港町として多くの人を引き寄せた。いろんな商取引があり、それが成立したら『よかったね』と料亭で打ち上げをする。それで各地へ帰っていって、また集まる。このコンベンション文化、料亭文化が新潟市の生業。若い人たちにはそれを何とか維持していってほしい。次代へのバトンはもう渡してあります。」
あおい:「すごいプレッシャーです。」
今井:「現実問題、柳都振興の社員が増えるとどれだけコストがかかるか、収益はどうなるかといった検討をしています。
それでさっきも言ったような、お稽古ごとの徹底や、踊りの発表会などを柳都振興から提案して、商工会議所をはじめいろんな方が乗ってくださった。
ここ数年は、柳都振興が入っていた三業会館の老朽化という問題もありました。壊すか売却するかの瀬戸際に追い込まれて、いろんな道を模索しましたが、結局解体することになりました。三業協同組合と柳都振興は、かつて料理屋だった建物に移転することになりました。鍋茶屋さんの近くです。
そこで、観光客向けに何かしたいと考えています。平日は柳都カフェを作って、柳都振興の振袖さんがお茶のお運びをしたり、土曜日は踊りを披露したりして、古町芸妓と触れ合う機会をつくる。古町芸妓は新潟の大切な宝なんだけど、会いたいと思ってもなかなか接する機会がないんですよね。
市山流のお師匠さんや老舗料亭の有明さんとも一緒になって、鍋茶屋から3軒を観光客が集まる場所にする。金沢のひがし茶屋街と言ったら大げさだけど、ある程度の観光名所にはなるかもしれない。外国人旅行客にもうけると思います。これまで新潟の経済界にはお世話になってきたので、この移転をきっかけに、柳都振興が何か恩返しできればとも考えています。
これをするにはやっぱり人手が必要で、今年は4人入社します。柳都の採用活動をテレビ局が追っかけてくれたんです。今回入社する女の子の一人は、柳都振興をテレビで見て、『新潟だったら、大学を卒業してからでも芸者になれるんだ』って分かって、沖縄から入社試験を受けに来てくれたんですよ。周りからの応援が、一つの形になり始めていると感じています。」
花街文化を支えてきた人々にとって古町芸妓とは何なのか

中野:「新潟唯一最大のキラーコンテンツ。美しい景色は他の場所でも見られるかもしれない。でも料亭を含めたこの文化は、オンリーワンだと思います。」
行形:「よそを悪く言うわけではありませんが、古町芸妓の特長は、お座敷で初めて会っても新潟花柳界の独特の柔らかい話し方で、距離感がすっと縮まる。何度も会っているような雰囲気を作り出せるんですよね。親しみやすいってよく言われます。」
高橋:「港町なので、よそから来た人を歓迎する風土が昔からあると思うんですよ。地元の方が連れて来てくださったお客様のためにお勤めするという精神がありますから。」
たまき:「あにさまっていう言葉がいいですよね。」
行形:「尊敬と親しみがこもった言い方なんです。『あにさま』『あねさま』は。」
高橋:「料亭にとっては、古町芸妓は大切な協力者。私たちが舞台を用意して、彼女たちが来てくれて初めて、お座敷が成り立つ。」
たまき:「生まれてからずっとこの世界なんですが、とっても恵まれたロケーションの中で働かせていただいていることがありがたいなと思っています。鍋茶屋さん、行形亭さんのお座敷で踊れるということが誇りです。」
あおい:「これから先もずっと携わっていきたいと思っています。古くから大事にされてきたものを、今私たちが教えていただいて、預かっているという感覚。新潟おけさや三味線、ふすまの開け方、着物の着方、お客様との話し方など教えてもらったすべてのことが私の財産です。これを未来にも伝えていきたいし、もっと発展させたいと思っています。」
今井:「新潟の宝物であることは間違いない。こんなに親しみやすい花柳界は他にないと思います。ただ、花柳界はごく一部の人しかまだ足を踏み入れていない場。だから、もっと多くの人に良さに触れてもらいたい。古町芸妓や料亭文化はこれからもっと人が集まるし、変わっていくと思います。とても楽しみですね。」
伝統の継承が危ぶまれるほどに数を減らした新潟古町芸妓。しかし、古町芸妓や花街文化を愛する地元の人々によって、その燈火は絶えることなく守られてきた。少子高齢化、人口減少、そして外国人客の急増により、日本の産業はもはや国内需要の視点だけでは語れない。変わりゆく時代にあっても、古町芸妓はしなやかに軽やかに荒波を乗り越えていくのだろう。新しい拠点の完成が待たれるばかりだ。
柳都振興株式会社
所在地:新潟市中央区西堀前通9番町1538番地 三業会館前
事業内容:芸妓の養成および派遣
新潟三業協同組合
所在地:新潟市中央区西堀前通り9番町1538番地 三業会館
事業内容:芸妓の福利厚生、技術向上の支援、三業会館の運営等
