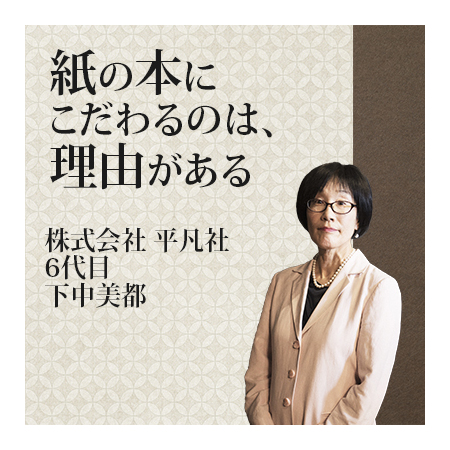
- 2020.10.02
「百科事典の平凡社」紙の本にこだわるのは、理由がある
株式会社 平凡社
オープニング・創業の精神 ~家訓や理念誕生の経緯~
今回のゲストは株式会社平凡社 6代目下中美都。1914年創業、日本の知識の礎として創創業の書である「や・此れは便利だ!」をきっかけに人文社会・美術・歴史・自然科学…と様々な単行本、そして事典を手がけてきた「平凡社」。
そんな中でも、社の象徴とも言える、「世界大百科事典」と「国民百科」の刊行は、のちに「百科事典の平凡社」と呼ばれ、現在では冊子の百科事典を刊行する日本唯一の会社へと押し上げるきっかけとなった。
――名前は平凡でも作るものは非凡――
その言葉通り、過去の蓄積にもとづき、現代を映し出す、温故知新の編集力そして、役立つ教養、わかるよろこび、を伝え続ける責務、その集大成で、この国の文化を「美しい本の形」に残し続けている。
今回は、取締役社長・下中の言葉から、平凡社が紡ぐ「歴史」や「伝統」に隠された物語、そして「長寿の知恵」の真髄へと迫る!
石田:本日のゲストは、株式会社平凡社 代表取締役社長 下中美都さんです。
よろしくお願い致します。
一同:よろしくお願い致します。
朝岡:この番組に女性の社長がいらっしゃったのは、下中さんが初めてなんでございますが、平凡社でも女性の社長っていうのは初めてですか?
下中:はい、初めてです。
朝岡:あー、そうですかー。まぁ、色々ね、本をお出しになっているのは、重々知っておりますけども、やっぱり事業としては、出版ということになりますよね?
下中:はい。
朝岡:平凡社といえば、やっぱり百科事典というイメージがとてもあるんですけども、、、
下中:ありがとうございます。
朝岡:やっぱり、百科事典をそもそも扱うようになったというか、出版するきっかけって何かあったんですか?
下中:創業者が下中弥三郎と言いまして、私の祖父にあたるんですけど、弥三郎の悲願というか念願というか、それで勉強して、百科事典がなければ、多分出会ってなければ、今、平凡社もないだろうといことがありまして。
小学校3年しか出てないものですから、家が貧しくて、ですから、百科事典を隣のお医者さんにもらって。それで家は、焼き物を焼く、丹波篠山の立杭の里の焼き物を焼く家なんですけど、お医者さんから貰った百科事典を窯の火で勉強して、それで、これさえあれば学校へ行かなくても勉強できると思って、田舎から出て来て東京で出版社を興したという話なんです。
朝岡:偉人伝にあるじゃないですか。そういう少年の頃のそういう何か苦労なさったっていう、そのまんまかなって
下中:日本昔話みないな(笑)
朝岡:そうそうそう。
下中:すごく恥ずかしいんですけども
朝岡:何かとても印象深いお話ですよね
石田:その百科事典ですけれども、下中社長は、その百科事典の魅力はどういったところにあるとお考えですか?
下中:「あ」から順にアトランダムに並んでるじゃないですか。
例えば、「カモノハシ」で引くと、次が「賀茂真淵」だったりして、なんか全然違う世界に入っちゃうっていうか。寄り道感っていうかワクワクする。
つい隣を読んじゃって、可愛い絵があると、次々読んじゃって、あれ?私は何を調べたのかしたら?っていう、そういう何か直ぐ役に立つわけじゃないんですけども、一つの項目を読むとその成り立ちがわかるように百科事典って編集されてるんですね。
所謂、スマホで調べてっていうことよりも、もうちょっと深く、調べたかったことの背景と知識の体系になってるというか、「あ」から「ん」まで一応選んで、何を選ぶべきか、何が大事か、そしてこれは何と繋がるのか、つまり、物事の繋がりがわかるっていうことが、おもしろがる力がつくようなそんな書物だとは思うんですけれども。
朝岡:なんか遊園地に居るようなものですよね。ここ新しいなって思って横見るとメリーゴーランドがあって、でも、メリーゴーランドと違うこっちの乗り物と、全然違うけど両方おもしろくて、なんか色々グルグル回ってるうちにドンドン広がっていくみたいな。
下中:そうそう、そうです!どっから来たかわからなくなるけど、まぁ、それはそれでね。
石田:そして、今こちらにですね、平凡社さんの書籍をご用意頂きました。こちらには、クラゲの図鑑なんか!
下中:ははは(笑)クラゲの図鑑て、ちょっと見て頂いて、宇宙船みたいでしょ、これプランクトンから全部入ってるんですね。クラゲの一種に入るんですね。プランクトンってクラゲの扱いになっていて、宇宙みたいな写真じゃないですか?
朝岡:ほんとにこれ、宇宙の星を見ているような!
下中:ミクロとマクロを行き来するような気分になるような不思議な。
これ全部日本のクラゲが全て入ってるんですね。これを編纂するのに、10年かかってるんですよ!10年かけてやりなさいって言ったわけじゃなくて、1〜2年で出来ますって、じゃあ始めてって言ったら10年かかったていう(笑)
もう全部そんななっちゃうんで、なかなかそのこんな大きくするつもりなかったんですけども。
朝岡:でも、これ見たら、決して「あ、クラゲ、そう。」って感じにはならないですね。
見たら、ページ開いたら「えぇぇ!!」ってなって、次また見て「おぉぉ!!」ってなって、また次開くじゃないですか。で、気がついたら30分1時間すぐ経っちゃうみたいなね。
こういうのが正に、百科事典的な楽しみ、知の世界なんですけど、平凡社というと、私なんかは「別冊太陽」などもね、大変好きで。
下中:(「別冊太陽」のシリーズの中の本である「草間彌生」の本ですが)今、大人気の草間彌生さんて、グッズ買うのに50分待ちとかですよ。今ちょうど展覧会やってる。
朝岡:こういうやつですね。これもまた、草間さんが表紙だから余計に印象深いんですけど、でも、このもともと「太陽」って雑誌がね、ありましてね、それでこの別冊の世界なんで、またちょっと違った。
下中:これ、ムックの「太陽」で、今言って頂いた「月刊太陽」っていうが1963年に創刊されて、このムックの「太陽」は1973年に創刊されて
朝岡:これもね、読み始めたら好きなあれが止まらないんですよね。
下中:あと、1冊を深めるっていう。入門だけれども、深いところまで読者を連れていけたらいいなって思って一つ一つ編集をしています。
朝岡:今はね、逆にコンピューターがあまりにネットとかも発展しちゃったもんですから、書籍としての百科事典っていうその意味が、もう一回問い直されてるような時代ではないかとも思うんですが。
下中:デジタル化は90年からやっています。
今はやっぱり、百科事典ってこんなですから、住宅事情でかつては百科事典を応接間に並べるっていうのが、インテリアみたいに「一家庭一百科」っていう宣伝文句でとっても売れた時代あったんですけど、今はもちろんデジタルの方が便利です。
ですから、今は、百科事典は、今一番使いやすいのは、ジャパンナレッジっていう日本のすごく優れたレファランスていうか辞典類を集めているサイトがあって、そこに搭載しているので、だから、百科事典と日本国語辞典を一緒に調べられるとか、だから、デジタル化はして使って頂くようにはなっています。
まぁ、紙の百科は紙の百科で、やっぱり図書館では必ず置いていただいて、ということはあるんですけど、だから、今ほんとに多様化してるんですね、書籍の形態が。紙もあれば、電子もあるし、それに向く形態を探してるっていう、その丁度過渡期の時代ではないかと思います。
それで、百科はやっぱりデジタルが向くので、いち早くやってきたとことはあります。
石田:そして平凡社さんは、もちろん百科事典だけでなくて、写真集だったり、そして新書も出していらっしゃいますよね。
下中:百科事典は創業者が一番最初に作った本ですけど、世界美術全集>であるとか、社会化辞典であるとか、書道全集であるとか、百科事典も児童百科であるとか絵本百科事典であるとか、それから百科以外では、東洋文庫っていうあまり知られてないんですけど、1963年に創刊されたアジアの個展叢書ということで、知る人ぞ知るシリーズがまだ今も続いていたりとか、さっき言って頂いた「太陽」があったり、それから、平凡社新書。こういうのもあります。
あの所謂、色んな知識、知のベースに色んな出版物が生まれてきているということがあって、何に特化しているということはないんですけど、調べて基準になる、知の基準になるものを作りたいということはあります。一貫して。
朝岡:なるほど。
ここからは各テーマをもとに6代目下中美都の言葉から平凡社がもつ長寿企業の知恵に迫る。
最初のテーマは「創業の精神」
創業者の想いを紐解き現在に至るまでの経緯、百科事典そして数々の書籍誕生の裏に隠された物語に迫る。
下中:今年103年になるんですけども、最初の1冊が「や・此は便利だ」という、いわば現代用語の基礎知識のようなものなんですけど。まぁ、これは弥三郎が書いた、著者なんですね。
朝岡:創業者が。
下中:ええ。1930年に百科事典初めて作るんですけども、百科事典を1回作ると情報をドンドン新しくしていかないといけませんね。
だから、改訂版、改訂版を作っていくんですけど、つまり百科を作ると、最初の百科は1000人の著者と仕事をしましたから、つまり理科の先生、所謂国語の先生、色々会うわけですよね、その方々とご縁ができて、その方々とまた本を作ったりとか多様なものが、百科事典を出版してると多様な著者とご縁ができて、たくさんの本が出来るということがあって、そういう百科を作りながら、その中から文系・理系と色んな本ができていったということがあります。
一つは、さっき言って頂いた「太陽」という。ビジュアルで、つまり写真で文化が分かるというこの流れがあって、相当たくさんの写真集を出したり、写真て一つの軸だったんですけど、写真年鑑があったり、「太陽」がありますから、ですからビジュアルの百科事典と言ってみれば、っていうことがあります。
そのまぁ100年の歴史なので、つづめて言えば、そこでその時代時代に合わせた色々な本が出て来てるわけですが、今はもう親書であるとかそういう小さな本もたくさん出しています。
でもまぁ一貫しているのは、さっき申しあげた、物事のそもそもが分かる、今何故こうなのかが分かる、そういう本を作っています。
朝岡:ベースは百科事典で、そこからビジュアルなものもあって、そっから時代に沿って色んなものが今至ってるということですよね。
でもこの平凡社という名前は、考えてみるとね、とてもね、良い名前なのは勿論なんですけども、付けた時によく平凡社っていう名前をお考えになったなと思ったんですけど、これはどういうあれなんですか?平凡社の名前の由来は?
下中:平凡社のホームページを見て頂くと、「世界一平凡な名前の出版社」って言ってみんなに笑われてるんですけど、平凡って、創業者の下中弥三郎がわりと大風呂敷な人で、もうおっきなことが好きで、色々社名は何にしよう何にしようって悩んでるところに、奥さんの祖母にあたる下中みどりが、「あたな、そんな大風呂敷なことばっかり言って、平凡が一番よ、平凡はどう?」って「あぁそうか。じゃあ、平凡にしようか」っていう流れがあるんです。
で、その心は、弥三郎は高尚なことはやだ。高尚で何か独りよがりなそういうのはやだと。また、その俗に流れるのもやだと。あんまりその一過性の、今興味のあるそういうのじゃなくて、所謂、平凡って付けたっていうことが一つの平凡社のその後を作っていて、平凡って、スタンダードってことだと思うんですね、スタンダードってとても大事で、スタンダードがないと世の中が色々になってる時に、じゃあこれはどうなってるかっていうそういう意味もあるんじゃないかなって今は思っています。それは、その辺を私は汲んで、本を作っています。
石田:弥三郎さんから美都さんに至るまで、全て一族で経営されてきた?
下中:そうなんです。弥三郎は1914年に会社を興しましたけれども、で、その創業者は40年やりました。
で、7人子供がいたんですけど、2代目は私の父で、下中邦彦という、下中邦彦が30年やりました。そして、その後に…
朝岡:三代目が?
下中:えぇ(笑)叔父の下中直也が2年やりまして、兄が10年。で、従兄弟の下中直人が15年。そして、私が3年。
こうやって話してると、100年企業って言うけれども、おじいちゃんから一家総出で襷を繋いでるという、そういうところの100年企業なんですね。誰も下中以外、誰もやっていないという。
石田:そして、美都さんが就任された時にですね、平凡社さんのシンボルマークも一新されたそうですね。
下中:元は、マークはあったことはあったんですね、ごく初期に。
で、弥三郎は壮大な世界とか世界平和を志している人ですから、地球をまん丸くして、まん丸い地球を2つに割って、そこちょっと繋いで、Hマークのそういうマークを作っていたんですけど、ちょっと抽象的ですよね。分かり難いというか。
私は出来れば、今、大変変化の激しい時代で、これから何十年もものすごくガラガラ変わっていくその時代に、出版を続けていくのに、何かとても一番大事なのは、やわらかい発想だと思っているんですね。やわらかい、シンプルで、そう平凡でね(笑)シンプルでやわらかい、だけど何か新しくて何か明るい未来が感じられるようなという。それでこのマークを。(マークを出す)
朝岡:これが新しい方。マークですね。こちらがね。本が重なってるんですね。
下中:食パンみたいだって言う人がいるんですけど(笑)一応、これ本なんです。本が3冊。
朝岡:あーなるほどね。
石田:上に本が2冊乗ってる形ですね。
下中:そうなんです。
朝岡:これがあれですか。美都さんが社長におなりになった時に、新しく決められたマークで。
その他に何かお作りになったり、変えたりしたものってあるんですか?
下中:まずそのマークを作るにあたって、佐藤卓さんというデザイナーにさっき言った、頭がやわらかくて明るい未来というイメージのデザインをしてくれるのは誰かなと考えて、佐藤さんにお願いしました。
佐藤さん、平凡社でも仕事してますので、まぁその仕事の為に平凡社に来て頂いて、その本が、もうそれこそ本がこんなに積み上がって崩れかけている社内を見て、いちいち感動してくださって、「あぁ、こういう現場で百科事典が出来ているんですね。」こんなに、私は汚いだけだと思ったんですけども(笑)とにかくもう積み上がってるそれを見て、このイメージを作ってくれたんです。
で、その、せっかくだから、このこういう(トートバッグ見せる)
朝岡:あ、トートバッグ。
下中:トートバッグも作りました、100周年で。こういうもの作りたかったんですね。
で、出来ればその、平凡社って百科事典だっていうこうやって言ってくださる方はだんだん少なくなってきて、百科事典って何ですか?って人がいるんですね。テレビのバックに並んでるあれだよ!って言うわけにもいかなくて(笑)
それで、だから、その、つまり私達が目指している知の標準のようなことが、マークで分かるって、ビジュアルってとっても大事ですよね。ビジュアルマークで。しかもこれって、そんなに気難しそうじゃないでしょ。っていうものを作って、つまり私達が、作ってきたものが外から見える形で、創業の精神が、中の人もそれから外の人も分かるような形にするっていうのが、私が100周年で志したことなんです。
石田:美都社長が、初の女性社長ということで継がれたんですけど、女性ならではのご苦労もあったのではないでしょうか?
下中:出版業界って、本当に男性社会なんですね、それで、ただ、本を作る人は女性が多いんです。根気強くやるので、コツコツやるので、積み重ねて。わぁー!とかやらないで、本当に薄皮1枚ずつあれしていく(はがしていく)様な仕事なので、割と女性に向くんですね。
で、編集の現場は、女性が多いんですけども、経営者とかそれから営業の世界です、営業ってつまり本を売ってくれる人たちですね。あの人たちは本当に男性ばっかりなんですよ。
で、私は社長に就任する3年前に営業の現場に入って、そういう業界の集まりなんかに出たりしても、400人くらいの会合で、男性が泊まりがけの会合でね、男性が、お膳を前に青い丹前姿で、だぁーっと並んでるんですね。もう遠くの方は霞んで見えないくらい男性がいるっていうそういう世界。
そういうとこに飛び込んで、クラクラしましたけど、でもこれは考え直せば、女性が少ないから顔を覚えて貰えるのよ!
朝岡:あぁー、なるほどなるほど。
下中:あの、逆にあちらは覚えてくれるんです。でも私は、おじさまはほんとに同じに見えることがあって(笑)こんなこと言ったら失礼なんですけど、やっぱりいっぺんに10人くらい会うと、名前覚えられないですよね。だから、名刺が3枚出てきたりしてあぁ悪かったな「初めまして」って言って、「こないだ会いました!」とか言われて、そういうことあるんですけど、だから逆に覚えて貰えるっていうメリットがあるっていうふうに思っています。
朝岡:でもね、良い方に考えればね、開けてくるってことですよね。
それにしても、下中さんは、そのまぁ、おじいさまが創業者でいらっしゃるし、代々下中のご家族というのが平凡社をやっていらっしゃったわけですけど、この業界に入るのはもうちっちゃい頃から、こういう出版業界にいくのは当たり前っていう雰囲気だったんですか?それとも、何か具体的にあって、で、何かこう出版の世界を志されたってことなんですか?
下中:えっとですね、さっき、下中家一族で襷を渡したという(話をしましたが)私の一つ上の兄がおりまして、兄は10年やったんですけど、下中弘といいまして。彼は、百科事典を「あ」から「ん」まで読んだ人なんですよ。つまり百科事典を読んだ歩く百科事典になっていて、で、本が好きで、自分の部屋を天井まで本にしていたと。私は何でも、お兄さんに聞けば何でも教えてもらえるというんで全然勉強しない子で、だから、兄がやるだろう!というのがありましたから、私が継ぐというのは思ってもいなかったんです。
ですから、とはいえ本が好きで、料理が好きだったんで、あの…お恥ずかしいんですけど、くまのプーさんとか好きで、くまのプーさんの料理の本を出している文化出版局っていうところに入ったんです、最初に。
で、そこはファッションの殿堂で、ファッション雑誌「ミセス(MRS)」とか「high fashion」とかそういうことをやりました。で、そこで17年も居たんですけども、その間にもうあらゆるデザイナー、色んな人たちのインタビューをして、インタビューして原稿を書くというのを膨大にやったんで、その点あの、なんていうか、対面の力はついたというか、人に会うのがすごい好きになったというそういうことはありますね。
そうこうしてたら、兄が平凡社に助けてくれないかというんで行ったということなんですけど。で、入ってすぐ、もうちょっとしたら、兄が従兄弟に渡したというそんな流れで、で、従兄弟が15年経ったら、もうそろそろ美都さんがやりなさいって急にまわってきて驚いた。そんな流れです。
石田:そうですかー
続いては平凡社に代々受け継がれし家訓や理念、そこに隠された想いに迫る。
下中:出版ってつまり言葉を遺す仕事なので、家訓ってわざわざ書くこともないんですね。
でも、家訓って言い方はされてませんけど、一番の、下中弥三郎がこの会社の一番のベースとなるとう言葉で遺しているのは、「出版は教育である」という言葉です。彼自身が窯の火で勉強して、ていう。それから、誰もが勉強する学習権ていうんですけどね、誰もが学ぶ権利があるっていう、それこそマララさんが「1本のペンが、1冊の本が世界を変える」って言ったじゃないですか、あれに似たような流れがあったと思います。ですが、家訓ていう形では、特には遺っていません。
朝岡:でも、百科事典読むとなんとなくそうだなっていうことがいっぱい。それがね、受け継がれていくというか、自分で考え…
下中:まぁ、自分の頭で考えろってことですね。
朝岡:そうですか。企業の場合はよく社員に、企業の理念といいますか、考え方をいかに浸透させるかというのが大事なテーマだったりするんですが、平凡社はそういう特別なことはあるんですか?
下中:一応、社史を編纂しておりまして、社史はそのどういう考えでこういう本を作ってきたかっていうのが分かる様に編集してあります。
で、まず「六十年史」っていうのがあったんですね、これが尾崎秀樹(おざき ほつき)さんて人が書いたおもしろい社史なんですよ。で、私はそれがあるお陰で、歴史を、社の歴史を勉強できました。
で、それをベースにありまして、さっきの2代目の下中邦彦という私の父、この人は第2創業者だと思っているんですけれども、彼が亡くなった時に、私はもう平凡社に居ましたから、「下中邦彦」っていう薄い本を作ったんです。ここに歴史、それから彼が何を考えてこういう「太陽」を作ったのかとか全部入っていて、これを自分で編集して社員に配るということをしました。
あともう一つは、100年を迎えるにあたって、スーパーOBを3人、スーパーOBに声掛けて、「百年史」を編集するのにっていうんで私も入って4人で「百年史」、これを編纂しました。
だから、平凡社を知る百科事典みたいな、またさっきのクラゲじゃないけど、またこんなに大きくなっちゃってどうするんだっていうことで、これは社員に100年の時に配りました。あの、ですから、その他はまぁ、私が昨年から毎月朝礼で、平凡社はこういう本が出たけど、どういう意図で作られているか。
それから、今の時代、この変化の激しい中でこうすべきだとか。心がけることは、なるべく言葉にして話すようにしています。それから、社員に片っ端から声掛けてお昼誘って、「ねぇ、あなた今何考えているの?」とか「どういう本作りたいの?」とか、2周しましたかしらね、順々に全部。スケジュールに入れて。
で、サシで話すとやっぱりみんな面白いこと言うんですよ。「この子こんなこと考えてたんだ」とか、それから「あなたがこないだ作ったこの本はこのように面白かったけれども、これはこの後どういう、この著者で他にアイディアあるのか」とか、そういう実際にどういう本を作るかっていう話にまで繋げてやり取りをしています。
朝岡:やっぱり活字とね、直接コミュニケーションとね、そういう形で。
下中:やっぱりね、サシでやらないとね、これが人数が増えるともうだめなの。サシが良いんです。対面しか方法はないです。今ね、電話とかね、なかなか人に会わないっていう仕事が増えてますけど、やっぱり対面が一番大事ですね。
で、私はインタビューを山ほどやった前の会社の多少の経験が活きて、インタビュアーとしては今でもすごくそういう人に話を聞くのが好きなんですよ。
決断 ~ターニングポイント~
続いてのテーマは決断、ターニングポイント。
過去に苦難それを乗り越えるべく先代たちが下した決断とは。そこに隠された想いに迫る。
下中:出版は、山あり谷ありでいっつも危機なんですよ。そういう意味じゃ、どれを話したらいいかなって思うくらい。
100年の歴史の中で、潤ったのって25年くらいしかないんですね。あとはいつも本を作る為に金策に走ってる。ってことはあるんですけど、その中でも特に大きなものは、一番最初は、弥三郎がつまり百科事典を作ったってとこなんですけど、1931年です。ちょうどその頃は平凡社はもう美術全集とか大衆文学全集とかね、結構当たった企画があって、で、ちょっと弥三郎も調子が良いなと思って、雑誌「平凡」っていう、平凡ってありましたね(笑)雑誌「平凡」っていうのを作るんですよ。
朝岡:それはもう1900何年ぐらい?
下中:5号で終わった雑誌ですからね、1931年(笑)
朝岡:あぁ、もう戦前のね、昭和の始めの方ですね。
下中:それは美術みたいな雑誌だったんですけども、雑誌を作るのが、その頃講談社が「KING」とか出したりしてて、やっぱり経営者としてはそういうことがやりたかったんでしょうね。
で、雑誌「平凡」っていうのを作ったんですけども、ところがまぁ、宣伝も色々工夫して、平凡をレコード作って、マーク作ったり、平凡の歌なんか作って、それをキャバレーで流すとか色んな工夫をして、平凡宣伝隊みたいな作って、
朝岡:キャラバン隊みたいな作った!キャラバン隊みないな!
下中:そう!それでこんな看板、写真を見ると、平凡って書いてあるのを背負ってみんな自転車に乗ってるっていうそういう全国行脚とか。それから、それがいつ帰ってくるかって懸賞を掛けたりとかそんなことをやったんですよ。
だけど、やっぱり、雑誌としてはスキルが足りなかったんでしょうね。5号で…
朝岡:5号で終わっちゃった
下中:5号で終わって、それで、そのさっきの宣伝隊は、もうどっかうんと遠くまで自転車で行ったところで、母屋が潰れちゃったってすごすご帰ってきたらしいんですけど。
まぁ、そうやって「平凡」で、経済危機、経営危機ですね。不当たりってやつですね。不当たりを出しそうになって、それで、どうしたかっていうところで、そこで弥三郎は、つまり自分が悲願だった百科辞典を、債権者集会ってやるんですね、ああいう不当たりなんかが出ると。その会議の席上で「皆、誠に申し訳ない。皆さんに迷惑をかけた。
しかし、私には素晴らしいアイディアがある。絶対に当たる企画である。それは百科事典を作ることだ!」って言って、堂々と話したんですよ。最初は、債権者会議の皆さんは「えぇー、あんな潰れかかってんのに百科なんか無理だろう」って思ったところが、でも、引き込まれて、あまりに、やっぱりそれは悲願でしたから、窯の火で読んだのがね。
だから、そこで百科事典があの人ちょっと結構真剣かも本気かもってところで、やらしてみようじゃないかってところで、6月の債権者集会があって、もうその暮れには、100刊の1刊目を出したんです。
そのためには、そのつまり印刷も写真植字っていう新しい方式とかテクノロジーも駆使してやったんですね。色んなことを工夫して本当に出したんです。で、それは売れたんです。
ですから、その転機ってことで言えば、平凡の転機。いずれ百科をやることになったとしても、その時にやれたってことは大きくて、そういうことが最初の危機ですね。
朝岡:ピンチの時にあえて
下中:そうです、そうです!
朝岡:大百科辞典をたちあげて
下中:ピンチをチャンスっていうのは、もう平凡社の全員心がけていることで。
朝岡:すごいね!そりゃ、創業者がおやりになってるからね。それはまた、伝説の
下中:その後また厳しくなったり、山あり谷ありなんですよ。
続いては6代目下中美都のターニングポイント。
下中:えっと私はまだ社長になってなかったんですけども、編集部長でしたか、2000年の時に、もう残念ながら、さっき言って頂いた「月刊太陽」これがみんな良い雑誌だって言ってくださるんですけども、やっぱりこう、それほどは売れないんですね。そこそこは売れたんですけど。
で、それはずっと言われてたんですけども、「太陽は売れないじゃないか」と。それはその、2代目の社長の下中邦彦が、これも悲願でやったんですね、「太陽」。だけどもう、ほんとににっちもさっちもいかなくなって、で、私の前の社長の時代ですけど、私は編集の責任者でしたから、もうこの際「太陽」を休刊するしかないっていうことになった時、これはやっぱりとても、とてもショックでした。
何故かっていうと、「太陽」って雑誌は、平凡社の出版物の柱を全部カバーしてるんですね。一つには、世界と日本の旅人の視点。二つ目には、伝統文化のビジュアル化。三つ目には、アートをお家で楽しむ。四つ目には、ポピュラーサイエンス。科学を分かりやすくする。で、五つ目は生活文化。これを、五つの柱に作ったのが「太陽」で、1963年で、残念ながら、2000年で休刊しました。
で、やっぱり辞めるとなるとスタッフも出て行ってしまうし、まぁそういうのはやっぱりね、悲しいことです。まぁ、ただ「月刊太陽」が休刊になっても、この「別冊太陽」ムックの「太陽」がありましたから、こちらをうんと増やして、つまり、月刊誌は休刊になったけど、ワンテーマで、これは雑誌。ムックですから遺るんですね。書籍みたいに遺りますから、だから、こちらは厚くして、「太陽」という柱は守りました。これは、でも、やっぱり辛かったですよ。
朝岡:ねぇまぁ、やはり平凡社の看板のね、雑誌でしたからね。だからこれを…でも、名前は別冊に遺してね、その辺がやっぱり経営者としてのやらなきゃいけない、辛くてもやらなきゃいけない仕事だったというね。
下中:でも、こっち(「別冊太陽」)は売れるんですよ。
何故かっていうと、一つのテーマを、そのテーマを知りたい人はそれを買うわけです。でも、雑誌となってると色々入ってるから。まぁ、特集主義なんですよ「太陽」って、だけど色々入ってるから誰もが買うわけじゃないんです。だから、一つのテーマに特化する方がよっぽど良いわけです。売れるわけです。はい。
石田:お伺いしたんですけど、社長はご病気もされたと…?
下中:はい。これは会社の経営とはあんまり関係がないんですけども、ちょうど10年前に会社の検診で引っかかって入院することになったんですね。で、とても健康だったからそういう体験もなかったんですけども。その時に、検診で引っかかったその帰りに、さっきのあれですよ、「逆境に合うと高い目標を立てる」ということにしているんです、私は。
だから帰りに、前々から、時間さえあればやりたいと思っていた、幸田文って、幸田露伴って言うんでしょ。幸田露伴の娘の幸田文さんって言って、しつけとか素晴らしい文章を書いてる「幸田文全集」をゲットして、で、それを、それで撰集を編むんだ!ということを。入院するときにそれを全集を持ちこんで、読んで、っていうことをしました。
つまり、やっぱり病気っていうのは、あんまり健康だから怖かったんですけども、だけど、「幸田文」を編むんだってことに気持ちをそっちに持っていくことによって、結果的に、私は病気は克服しました。全く健康になりましたし、だから、病気に負けないっていう。で、編集って寝ても覚めてもその話を、そのテーマを考えてるもんです。本当に夢枕に著者が立つ程、夢中になる仕事で、私は、その幸田文の撰集を作ったことで救われました。
まぁちょっとこの話は、ただそれは売れたのよ、13刷りかな。
朝岡:13刷り!
石田:すごいですね!
下中:で、6冊にしたんですけど「幸田文しつけ帖」っていう本は、やっぱり売れました。で、しつけって…あ、石田さんそういうことやって…マナーとかお詳しいですよね。
石田:はい、勉強させて頂いております。
下中:つまり、今しつけがもう…何ていうか、しつけっていうよりも、好きにさせるって感じですよね。
朝岡:放任しちゃう。しっぱなしが多いから。
下中:ですけど、幸田文さんの言葉は、実にあたたかく厳しく、しつけがどのようにお父さんから行われたかってことが書いてあって、それは今の世の中に欠けていることだから、是非今の人たちに読んでもらいたい。
これ、絶対今の世の中に役に立つはずだっていうその信念で編集しました。
朝岡:もうだから、おじいちゃまがピンチの時に、会社がピンチの時に大百科事典を打ち上げたのと同じように
下中:いやいや、全然、小粒ですから(笑)
朝岡:あの下中さんもやっぱりあれです、ちょっとまぁご病気の時にね、また新たな志をバーンとぶち立てて、それを頑張ってやったら、健康にもなったし本も売れたっていう。
下中:そう言って頂くと、なんかお恥ずかしい感じがしますけど(笑)
朝岡:いやいやいや。
石田:ほんとにその前向きなそのパワーに、もうほんとに大尊敬です。もうほんとに憧れます。
朝岡:斯く生きるんだ!みたいな感じですもんね。
下中:いやいや、もう逆境に課題を作る。これです。
朝岡:良い言葉だ。
石田:ねぇ!逆境に課題を作る!
朝岡:逆境にめげちゃだめなんだ、逆境に課題を作る!
下中:はい、そうです。目標を作れば良いんです。
言魂 ~心に刻む言葉と想い~
言魂。心に刻む言葉と想い。
強い想いと信念が込められた言葉には魂が宿る。
人の人生に大きな影響を与える。下中美都が家族や知人から受け取った言葉、そこに隠された想いとは。
下中:私は、二代目の第二創業者と思っている下中邦彦。この人は「太陽」も作ったし、文化的地固めをした人なんですね。
平凡社と言った時に多少ちょっと文化的なイメージを持ってくださるというのはその2代目が作った頃なんですね。でも二代目は、下中邦彦は、やはりこれも、こうしろとは一言も言わないんですけど、背中で教えるっていうところがあって、彼の生き方を見ていると、それから私こうしろとは言わないけど、一つだけ言えば、「自分の頭で考えて、自分の言葉で話せ」ということを教わったと思います。
つまり、受け売りじゃない。石田さんがこう言ってたから私もこう思う、じゃないんです。お聞きした、その中から自分から出て来た言葉、それが自分の知恵だっていう、そういう風にしてきました。それは、自然とそうなった環境だったと思います。
朝岡:スタイルがね、スタイルがこう学べるっていうのは良いですね。
言葉だけにしちゃうと、その言葉をどう解釈しようみたいなことになっちゃうんだけど、スタイルって言うのは、もう自分なりにこうなんだなって思って生きている糧にできますよね。
下中:でも、朝岡さんもきっとそうだと思いますけど。
朝岡:いや、私はね、今日は何か、下中社長から色々学ばされて(笑)なんか百科事典読んでるような気持ち(笑)
下中:とんでもない。
石田:良い授業を受けてる感じですよね。
ここで、今現在ですね、社長が心に留めてらっしゃる言葉はございますか?
下中:私は、社長になる直前からもう誰も叱ってくれないんですよね。社長になったということは、つまり、物事の基準を作る人になることで、私が何かしない限り何も起こらないということになります。だから、ものすごく考えるようになりました。
考え続けるのが仕事だっていうようなことを思ったりとか、まぁこうした方がいいなってことを色々、あの、そうですね。まぁこういういつもこういう手帳を持っていて、
朝岡:ご自分の手帳でいらっしゃる?
下中:ええ。これ、だいたいそのこれが17冊目になってますけど、思いついたこと。ニュースで聞いて、今起こっているあの現象はこうすればいいんだとか、その自分から出て来た言葉をずっと書いています。
で、それをあのずっと書いて、時々こうやって打ち出して、自分でこうやって言葉。で、それを300くらい貯めて、時々読み返して、でもこれは自分の為のことなんで、自分がこれから更に判断していく時に、自分の為の自分を叱るみたいなことがありますから、でも、そういうことをしないと、判断の基準を作る人ですから、私は。だから、その前にこう言ったことは、遺さないといけないですよね。だから、違うことを言ったらやっぱりいけないので。
だから、いくつも、そうですね…私が一番考えていることはですね…「社長は判断の基準を作る人」ってことですね。それから、「考え続けるのが仕事」。それからもう一つ挙げれば、「新しがりやと古がりや」出版社にはこの両方が必要なんですね。最先端とそもそもみたいな。
で、新しがりやの人って、もうそれこそ、もう新しいニュースがもう俺はも一刻も早くこれを知ってるっていう感じで、これも大事なんです。そういう真摯の気持ち。だけど、それはじゃあどっから来ていて、古本を見ながら、それはこういうことから来ているんだよって答える。っていうその幅が必要なんですね。
ですから、平凡社みたいなスタンダードを作る。つまり、知識の、知恵の基準を作ろうという出版社は両方が大事なんです。だけど、こっち(新しがりや)は、古がりやをあいつらな!って思うかもしれないし、古い方は、あいつら新しいこと言って!って。やっぱりそういうところのバランスを取るのが大事だと思います。
で、これは、結構難しいんです。やっぱりプライドをかけてみんなその仕事をしていますから。
だけど、そのために一人一人のさっきお昼に誘って、この人は今どの辺りにいるのかとても気を付けながら、それから、その人が困っているとこは何かとか、そういうことも聞きながら、またノートに書いたりとか、それを覚えていて、あの問題はどうなったかって、次にお昼を食べる時にまた聞たりとか、やっぱり言葉を遺しておかないと、やっぱ社長って、出版社の社長って出来ないなって思っています。
朝岡:なるほどね。
NEXT100 ~時代を超える術~
NEXT100、時代を越える術。
革新続け100年先にも継承すべき核となるもの。
平凡社6代目下中美都が語る次代へ届ける長寿企業が持つ知恵とは。
下中:私ね、やっぱり、紙の本っていうのは、さき程、電子も便利とか、その色々な…例えばコミックとかラブストーリーは電子でもバンバン読みたいわよねとか色々なんです。やっぱり紙の本で、自分で読んで、自分で考える。自分の頭で考えるという、そういう心に一番ゆっくり届く言葉を編集したこの紙の本というもの。これはやっぱりコアになると思います。
色々、あの色々作りますけど、何で紙の本が良いかって言うと、やっぱり、本は人なんですよ。
で、本を読むとその人、朝岡さんの本を読んだら朝岡さんに会ったみたいに思うわよね。本は人で、人の心の容れ物として紙の本は最上のものです。そういうやり取りをして読める物です。真空の気持ちで読むし、だから、人の心が入っている。
それから、知恵の容れ物としてやはりこれは最上のものだと。これ以上のものはないと思います。知恵の容れ物っていうことでも必要です。
それから、手渡せるじゃないですか。知恵を。勿論、電子も勿論良いんですけど、手渡せて、この知恵っていう人類で一番宝ですよね。だって、建築だってお花だって何だって無くなりますけど、知恵がもし伝承できたら、それ以上に良いものってなくて、それがちょうど良くこれくらいのものに編集して、それを石田さんにあげられるとか、そういうのって紙の本以外にないかなと思います。
勿論、この紙の本で編集したもの、電子でまたってこともありますけど、だから、コアはやっぱり書籍だと思っています。
朝岡:紙の本はずっと100年先まで。ちゃんとあるという。
下中:そうですね。紙の本は500年ですから。グーテンベルクから。
朝岡:あぁー!そうですね。
下中:で、工夫されてるんですよ。読みやすく、丁度良く、編集も起承転結、ちょうど良く盛り過ぎないでとかね。だから、そういう実績はあります。
勿論、その部分的に電子で読んだりとかすごい多様な読書。多様なライフスタイルの中で、読書は変わってきますけど、その中で紙の本の良いものを最後まで作っていく出版社でありたいと思っています。
で、これは電子がどうっていうんじゃないんです。選択肢の中でやっぱり良いものを作らないと遺らないんですよね。
紙の本が云々って、紙の本が売れなくて大変なんだってねってよく言われるようになったんですよ。それは2010年の電子書籍元年の時に。で、紙の本が無くなるなんて誰も思わないんだけれども、それが、ニュースで伝わって、出版社大変なんだってねって、全然知らない業界の人に言われて、でもそれは、それでもやっぱり、本という色んな形があるけど、良いものを作っていくのが私の使命だと思っています。
石田:先程、編集者の方に女性が多いって仰ってまして、あれ、根気強さという女性のそういう特性が活かされる現場って仰ってたんですけれども、これから先ですね、出版業界において、女性の知恵だったり、そういうパワーっていうのがより必要になるとお考えでしょうか?
下中:変えるもの、変えないものということで言えば、変えるものの一つに、女性が経営に入って行くと良いとこれは信じています。
なぜかというと、私は長年会議で長年紅一点でした。勿論、平凡社はマッチョな人いませんから、私を疎外するような人はいないんですけども、でもやっぱりちょっとね、考え方っていうか着眼点が違うんですね。ですから、私がこうしたら良いのにって言っても、男性陣はわからないんですね。それは、やっぱり男性の同調圧力もあるかもしれませんね。
それから、そういう意味では、女性の意見。私はもう経営に入って15年経ってるんですけど、私の意見あんまり、あんまり通ってきていないんですよ。それは、私の問題かもしれない、もっと自身をもって言えば良かったと思うんです。今でも社長になって、言いたいこと言ってますけど、っていうことは、今社長になって私が一番良いと思っていることは、人が私の話を真剣に聞いてくれるようになったんです。これは、私一生懸命考えて、毎日考えてますから、人が聞いてくれて、会社が少しでも良くなるように活かしてくれることすごく有り難いと思っているんです。
でもそれは多分、私が社長になったから、社長にならないと話が聞かれないのかってことないんですけど、多分女性の感性っていうのは、もっとこれから変えて行かなくちゃなんないってところでいえば、これから大変変化の激しい時代に入りますよね。
で、読書も変わえるでしょうし、その中で、女性は衣食住。着るものだって、今日素敵な服を着てらっしゃいますけど、今日これを着るっていうそういう感性。それから、今日は暑いからあれを飲みたいなとか。まぁ、衣食住に関して、女性はすごくこだわって生きているんですね。生きるセンスにこだわってる時って、男性がこだわらないって言ってるんじゃないんですよ!(笑)
でも、男性はそこまでこだわらないっていうか、感覚的に。そういうことっていうのをこれから作る。つまり、生きていく為の生きていくセンスを本にしていくとしたら、それはとても大事なんです。で、その為には、編集者が頑張っても限界があるんです。やっぱり経営全体が、女性の私が一人でいってもやっぱりダメで、やっぱりやり取りをしながら女性の感性を経営に入れて行くっていうことが、多分、会社を変えていけるんじゃないかと思っています。
で、勿論それによって、男性ももっと元気になっていきますし、そういう意味じゃ、男性が多い社会の中できましたけど、変えていけるんじゃないかと私は社長になって思っています
朝岡:ほぉー!かなりあれですね。具体的にこういうことをやるんだということがね、もう下中さんの中でふつふつと、こうたぎっている!って感じですけどね。
下中:百科事典って、「歳時記」って本があるんです。「歳時記」っていうのは、百科事典を季節で、時系列で編集したものなのね。
ああいうものは、やっぱり女性が作るのが得意で、うちでも、「くらしのこよみ」っていうアプリを作って、5日ずつ季節が変わっていくものの、それを発信して、それが全部できたら「歳時記」にしたっていう、これは所謂、時系列の百科事典ですね。それは防音デジタル。
デジタルから生まれた紙の辞典も作りましたけど、そういうことってやっぱり女性の発想でとか、これからもっと大事になるかなとは思います。勿論、男性の発想も。ていうか、男性と女性がもっとやり取り出来ることによって、全然違う展開があるはずです。
朝岡:までね!まだ出来る事いっぱいあるってことですね。
下中:と思うんですけどね、まだこれからなんですけどもね。
朝岡:まぁ、あの100年後にも、是非平凡社には存在して頂いて、色んな本を中心に出して頂きたいと思いますけども、まぁその100年先の人間に何か伝えておきたいというものがあれば伺いたいなと。
事業を続ける上での心得でも結構なんですけど。
下中:人は本に育てられます。間違いないです。そして、本より良いものはこの世の中にないと思っています。
これを100年後もやってもらいたいと思います。
平凡社、6代目、下中美都。
本は知恵の入れ物として最上のものである。自ら読んで自分の頭で考える。心に届く言葉を編集した「人の心」が入っている本を作り続けてほしい。
この想いは100年先の後継者に受け継がれていくだろう。